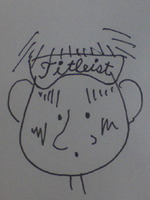2009年06月10日
「ミス」の捉え方
事業をしていると、当然、失敗やミスが生じます。
開発を請け負ったソフトが動かない。
販売した商品の内容が違っていた。
訪問の期日を間違えた。
いろいろありますよね。
もちろん、失敗やミスをなくすことは重要なのですが、なかなか減るものでもありません。
人間のすることですから。
だから、ミスや失敗をしたあとの対応力を磨くことが重要です。
ここで陥りやすいのは、「ミス」をしたことによる心理的影響に引っ張られること。
つまり、ミスをしてしまったから、相手方の言うことは何でも聞かないといけないという心境になってしまうことです。
それは違うんですね。
「ミス」は「ミス」。それについて、謝罪の意を示すことは当然ですし、自身の気持ちとしても申し訳ないという気持ちはなくしてはいけません。
だけど、そのことと、ミス後の対応とは、必ずしも直結しないのです。
相手方の要望には、ミス後の対応としては、過大なもの、不必要なものの要求が少なくありません。
それに応じてしまっては、自社のお金がいくらあっても足りないでしょう。
対応として、必要かつ合理的な範囲なものは必ずあります。
それは、法的な責任とビジネス的な責任を合わせて考えなければならないのですが、これくらいのミスには、これくらいの対応というのは、自然にみえてくるものです。
それ以上の要求は、やはり不当なものとして、きっぱりと拒絶できる。
それはそれ、これはこれ。と問題を切り分けられる能力とそれを相手に主張できる能力が、ビジネスには必要になってきます。
普通の営業マンに、それを求めるのは、今の日本ではまだまだ酷なようです。
ネゴシエーションは、やはり経営者の仕事となることが多いですね。
しかし、割り切りと思い切りで交渉をしようと腹を決めると、意外にすんなりいくものです。
厳しい交渉の矢面に立つこともある我々からすると、「ごめんなさいと心から思っていますが、これしかできません。」とはっきり言えないと話を進めることができないというのは、身にしみています(笑)。
あとは、いかに「これしか」できないと言いながら、相手にとっては、「これがいい」なと思わせられる理屈を準備できるかが腕の見せ所といえるでしょうか。
大事なことは、常にそういう交渉をする覚悟をもってもらうことですね。
そのためには、単に自社からみた解決策だけを考えるのではなく、第三者的にそのトラブルを捉え、判断することのできる俯瞰的な視点を持っておくことです。
その視点の一つとして、法的にどの程度の責任を負うことになるのかという知識を持つことも考えてもらうといいかも知れません。
開発を請け負ったソフトが動かない。
販売した商品の内容が違っていた。
訪問の期日を間違えた。
いろいろありますよね。
もちろん、失敗やミスをなくすことは重要なのですが、なかなか減るものでもありません。
人間のすることですから。
だから、ミスや失敗をしたあとの対応力を磨くことが重要です。
ここで陥りやすいのは、「ミス」をしたことによる心理的影響に引っ張られること。
つまり、ミスをしてしまったから、相手方の言うことは何でも聞かないといけないという心境になってしまうことです。
それは違うんですね。
「ミス」は「ミス」。それについて、謝罪の意を示すことは当然ですし、自身の気持ちとしても申し訳ないという気持ちはなくしてはいけません。
だけど、そのことと、ミス後の対応とは、必ずしも直結しないのです。
相手方の要望には、ミス後の対応としては、過大なもの、不必要なものの要求が少なくありません。
それに応じてしまっては、自社のお金がいくらあっても足りないでしょう。
対応として、必要かつ合理的な範囲なものは必ずあります。
それは、法的な責任とビジネス的な責任を合わせて考えなければならないのですが、これくらいのミスには、これくらいの対応というのは、自然にみえてくるものです。
それ以上の要求は、やはり不当なものとして、きっぱりと拒絶できる。
それはそれ、これはこれ。と問題を切り分けられる能力とそれを相手に主張できる能力が、ビジネスには必要になってきます。
普通の営業マンに、それを求めるのは、今の日本ではまだまだ酷なようです。
ネゴシエーションは、やはり経営者の仕事となることが多いですね。
しかし、割り切りと思い切りで交渉をしようと腹を決めると、意外にすんなりいくものです。
厳しい交渉の矢面に立つこともある我々からすると、「ごめんなさいと心から思っていますが、これしかできません。」とはっきり言えないと話を進めることができないというのは、身にしみています(笑)。
あとは、いかに「これしか」できないと言いながら、相手にとっては、「これがいい」なと思わせられる理屈を準備できるかが腕の見せ所といえるでしょうか。
大事なことは、常にそういう交渉をする覚悟をもってもらうことですね。
そのためには、単に自社からみた解決策だけを考えるのではなく、第三者的にそのトラブルを捉え、判断することのできる俯瞰的な視点を持っておくことです。
その視点の一つとして、法的にどの程度の責任を負うことになるのかという知識を持つことも考えてもらうといいかも知れません。
Posted by たばやん at 21:04│Comments(2)
│経営
この記事へのコメント
すごく面白くて,勉強になる記事でした.
自分が結構,ミスを犯したあとの対応が記事に書かれているとおり,なんでも聞いてしまうタイプです.
確かにミスを犯したときは,自分にすべての非があり,相手の言うことをすべて聞いて,それに従ってしまいますね.
すべて相手の言うことを聞くのではなく,自分でもしっかりとその後の対応をしっかりと線引きしないとと思いました.
自分が結構,ミスを犯したあとの対応が記事に書かれているとおり,なんでも聞いてしまうタイプです.
確かにミスを犯したときは,自分にすべての非があり,相手の言うことをすべて聞いて,それに従ってしまいますね.
すべて相手の言うことを聞くのではなく,自分でもしっかりとその後の対応をしっかりと線引きしないとと思いました.
Posted by DAI at 2009年06月14日 15:20
コメントありがとうございます。
日本だと、開き直りって結構悪い使われ方や印象がありますが、実は、大事なことなんですよね。
ミスはミスと開き直る。そこから改善が生まれるのだろうと思います。
コンプライアンスの意味がきちんと理解できていない企業は、開き直ることを是とせず、ミスを隠ぺいしやすい体質でもあることが多いように感じます。
日本だと、開き直りって結構悪い使われ方や印象がありますが、実は、大事なことなんですよね。
ミスはミスと開き直る。そこから改善が生まれるのだろうと思います。
コンプライアンスの意味がきちんと理解できていない企業は、開き直ることを是とせず、ミスを隠ぺいしやすい体質でもあることが多いように感じます。
Posted by たばやん at 2009年06月18日 20:11
at 2009年06月18日 20:11
 at 2009年06月18日 20:11
at 2009年06月18日 20:11