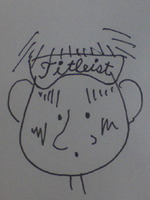2007年03月31日
すごい人の頭ん中
現在活躍中の、起業家11人のインタビュー集ですが、読んでみると11人ほとんどが結局、同じことをそれぞれの言葉で言っていることに驚きます。
成功の秘訣は、そんなに多くないようです。
私がこの本から読み取った成功のために必要なことは、
① 行動すること
行動する前から、ああだこうだ考えても、それだけではダメだということです。
(考えるなということではありません)
② 失敗から学ぶこと
それぞれ全員が大なり小なり、当初自分の考えていた結果とは異なる結果になる経験を積んでいます。大事なのは、そこから学び取って、次に活かすこと。
これができないと、行動しても意味がないようです。
③ 好きなことをやること
言葉は違いますが、全員がこの重要性を説いています。
「好きこそものの上手なれ」なのは、間違いないようです。
④ 成功するまで続けること
これが一番難しいですが、一番必要なことのようです。
続けることが出来るためには、それが好きでないといけないし、同じ失敗を繰り返さないと思って、新しい方法で行動する必要がありますから、続けることができる=①から③までを身につけたという方程式になるのかも知れません。
あと面白いと思ったのは、成功の定義です。
ここまで読んでくれた方は、自分の中にある成功の定義を各自であてはめて読んでもらっていたと思います。
成功を、イコール事業が大きくなることとした人や、大金持ちになることとした人等、イメージは人それぞれでしょう。
起業家11人もそれぞれ自分の中での「成功」の定義は異なっているようです。
自分の中で何をもって、成功と呼ぶかをまずしっかり考えることが、何よりも重要なのかも知れませんね。
2007年03月30日
買収防衛策、株主総会決議へ
サッポロの株主総会で、新買収防衛策が承認されました。
ニュースはこちら
サッポロホールディングスの買収防衛策についてはこちら
興味のない人にとっては、サッポロというブランドがどうなるか、外資にわたるのか程度の話かも知れませんが、日本のM&Aの歴史的には、大きなターニングポイントになるものかも知れません。
会社の買収防衛策については、大きく2つの視点から議論ができます。
①公開会社であること=誰でも株を買うことができないといけないのではないか
②取締役が株主を選択することができるのか
公開会社が一定数以上の株式の購入をどういう形であれ、制限することになるのは、「公開」の否定ではないかと考えられます。
買収されるのが嫌なら、そもそも公開(上場)するなという理屈です。
※「公開」と「上場」は厳密には異なります。
現に、サントリーのように従前から非上場としている会社もありますし、上場していた会社がMBOにより、クローズドカンパニーとなる(MBO:経営陣によるTOB等の株式買い付け。これにより株主数(比率)の関係により上場基準を満たさなくなることがあります)例も少なくありません。
すなわち、上場しているのであれば、株主の構成はどうでもよいというのが大前提となるはずで、それを制限すること自体許されないのではないかという観点です。
さらに、多くの会社で採用されている買収防衛策は、事前に買収案や買収後の経営方針等を開示させた上、それが企業価値を損なうものでないかを取締役会がチェック→取締役会の判断で対抗措置(新株発行等)をとるというものです。
これは、結局、株主を取締役が選ぶことに他なりません。現在の株主から委任を受けているとはいえ、新たに株主になろうとする者を、既存の株主から委託を受けている「だけ」(こう言っていいのかが論点ですね)の取締役が、選別してよいかという問題があります。主従が逆転してしまう可能性があるのではないかという観点からの議論です。
これらの問題を決することができるのは、会社の所有者たる株主だけです。
そのため、買収防衛策をわざわざ株主総会で決議するのです。
株主が決めたのであれば、それはその会社の最終かつ最高の意思決定に他ならないのですから、取締役会にどのような権限を与えるのかも他からとやかく言わせることもありません。
後は、多数決により、意思決定をした場合、そこからこぼれる少数者の権利を保護すれば足ります。(それについては、会社法である程度カバーされています。)
サッポロの決議は、株主に会社の意思決定権が戻ってくる、そのような流れを作る大きな第一歩だったと評価される日がくるかも知れません。
次は、アデランスでも株主総会での攻防が待っているようです。
スティールパートナーズの巻き返しがあるのでしょうか?!
ニュースはこちら
サッポロホールディングスの買収防衛策についてはこちら
興味のない人にとっては、サッポロというブランドがどうなるか、外資にわたるのか程度の話かも知れませんが、日本のM&Aの歴史的には、大きなターニングポイントになるものかも知れません。
会社の買収防衛策については、大きく2つの視点から議論ができます。
①公開会社であること=誰でも株を買うことができないといけないのではないか
②取締役が株主を選択することができるのか
公開会社が一定数以上の株式の購入をどういう形であれ、制限することになるのは、「公開」の否定ではないかと考えられます。
買収されるのが嫌なら、そもそも公開(上場)するなという理屈です。
※「公開」と「上場」は厳密には異なります。
現に、サントリーのように従前から非上場としている会社もありますし、上場していた会社がMBOにより、クローズドカンパニーとなる(MBO:経営陣によるTOB等の株式買い付け。これにより株主数(比率)の関係により上場基準を満たさなくなることがあります)例も少なくありません。
すなわち、上場しているのであれば、株主の構成はどうでもよいというのが大前提となるはずで、それを制限すること自体許されないのではないかという観点です。
さらに、多くの会社で採用されている買収防衛策は、事前に買収案や買収後の経営方針等を開示させた上、それが企業価値を損なうものでないかを取締役会がチェック→取締役会の判断で対抗措置(新株発行等)をとるというものです。
これは、結局、株主を取締役が選ぶことに他なりません。現在の株主から委任を受けているとはいえ、新たに株主になろうとする者を、既存の株主から委託を受けている「だけ」(こう言っていいのかが論点ですね)の取締役が、選別してよいかという問題があります。主従が逆転してしまう可能性があるのではないかという観点からの議論です。
これらの問題を決することができるのは、会社の所有者たる株主だけです。
そのため、買収防衛策をわざわざ株主総会で決議するのです。
株主が決めたのであれば、それはその会社の最終かつ最高の意思決定に他ならないのですから、取締役会にどのような権限を与えるのかも他からとやかく言わせることもありません。
後は、多数決により、意思決定をした場合、そこからこぼれる少数者の権利を保護すれば足ります。(それについては、会社法である程度カバーされています。)
サッポロの決議は、株主に会社の意思決定権が戻ってくる、そのような流れを作る大きな第一歩だったと評価される日がくるかも知れません。
次は、アデランスでも株主総会での攻防が待っているようです。
スティールパートナーズの巻き返しがあるのでしょうか?!
2007年03月30日
キューテックコラボ設立!
昨日、北九州市戸畑区の西日本工業倶楽部にて、九州工業大学技術交流会、「キューテックコラボ」の設立総会がありました。
キューテックコラボは、九工大の産学連携センターが中心となって、九工大と地域企業等、産学官の関係者が知恵を出し合う場所を作り、それにより地域の活性化を図るという趣旨のものです。
私も、九工大卒業生として、産学官関係者のはしくれとして(?)、会員にしてもらいました。
開催場所になった、西日本工業倶楽部へは、初めて行ったのですが、明治時代から刻が止まったような雰囲気です。

設立のスタートを、古き良き建築物で行うあたりが、九工大らしい感じがします。
もっとも、平日の昼間であったので、やむを得ないところもありますが、出席者に若手が少なかったのが残念です。
キューテックコラボの成否は、日頃、研究室にこもっている若手研究者をどれだけ外にひっぱりだせるかにかかっていると思います。
今後は、若手の参加が増えるように、工夫する必要があるでしょうね。
キューテックコラボは、九工大の産学連携センターが中心となって、九工大と地域企業等、産学官の関係者が知恵を出し合う場所を作り、それにより地域の活性化を図るという趣旨のものです。
私も、九工大卒業生として、産学官関係者のはしくれとして(?)、会員にしてもらいました。
開催場所になった、西日本工業倶楽部へは、初めて行ったのですが、明治時代から刻が止まったような雰囲気です。

設立のスタートを、古き良き建築物で行うあたりが、九工大らしい感じがします。
もっとも、平日の昼間であったので、やむを得ないところもありますが、出席者に若手が少なかったのが残念です。
キューテックコラボの成否は、日頃、研究室にこもっている若手研究者をどれだけ外にひっぱりだせるかにかかっていると思います。
今後は、若手の参加が増えるように、工夫する必要があるでしょうね。
2007年03月29日
金融商品取引法について(1)
最近、法律以外の話題ばかりが続いているような気がしていますので、今日はちょっぴり堅めな話です。
証券取引法は、以前から有名ですが、証取法の守備範囲を広げて、有価証券以外にも法の規制を掛けようとしたのが、金融商品取引法です。
名前のとおり、証券から金融商品へと規制の対象が広がっているのですね。
もっとも、この法律で全ての金融商品が網羅されたのかというとそうではありません。
先物市場取引や、為替証拠金取引は別の法律でカバーされる他、銀行法、保険業法による規制も残っています。
統一的な法規制を実施する方が、規制する側もされる側もコストが少なくすみ、合理的だと思うのですが、監督官庁という巨大な壁がそれを何重にも阻んでいるようです。
このあたりは、そろそろ本気でなんとかしないと、世界的なマーケットが同質化しつつある中、日本だけが取り残されるような気がしています。
さて、普通の生活をしている一般市民にこの法律が何をもたらすかというと、この法律で規制されている金融商品については、販売側に色々な義務が課せられています。
簡単にいうと、呼んでないのに訪問してはならない(商品によっては、この義務がないもののあります)、契約時にはリスク説明をきちんと行う、契約時には書面を作成する等々です。
つまり、投資の素人である一般市民については、原則として自分で望まない限り、金融商品をもったセールスマンが突然、家にはやってこない仕組みになっています。
もちろん、この法律等で規制されていない金融商品のセールスマンがやってくることはあります。
営業の自由がありますから。
しかし、この法律で規制されていない商品は、相当難しいスキームであったり、リスクが高いものであったりするはずです。あるいは、もしかしたら詐欺的なものもあるでしょう。
普通に生活する中で、この法律で規制されている以外の金融商品で、資産を運用する必要があることはまずありません。
向こうからやってくる投資話、金融商品については、十分注意してください。
この法律に対する知識として、まずは、投資は自己責任、国は基本的に金融商品を個別に売りにいくことを禁止しているのだということを押さえて下さい。
証券取引法は、以前から有名ですが、証取法の守備範囲を広げて、有価証券以外にも法の規制を掛けようとしたのが、金融商品取引法です。
名前のとおり、証券から金融商品へと規制の対象が広がっているのですね。
もっとも、この法律で全ての金融商品が網羅されたのかというとそうではありません。
先物市場取引や、為替証拠金取引は別の法律でカバーされる他、銀行法、保険業法による規制も残っています。
統一的な法規制を実施する方が、規制する側もされる側もコストが少なくすみ、合理的だと思うのですが、監督官庁という巨大な壁がそれを何重にも阻んでいるようです。
このあたりは、そろそろ本気でなんとかしないと、世界的なマーケットが同質化しつつある中、日本だけが取り残されるような気がしています。
さて、普通の生活をしている一般市民にこの法律が何をもたらすかというと、この法律で規制されている金融商品については、販売側に色々な義務が課せられています。
簡単にいうと、呼んでないのに訪問してはならない(商品によっては、この義務がないもののあります)、契約時にはリスク説明をきちんと行う、契約時には書面を作成する等々です。
つまり、投資の素人である一般市民については、原則として自分で望まない限り、金融商品をもったセールスマンが突然、家にはやってこない仕組みになっています。
もちろん、この法律等で規制されていない金融商品のセールスマンがやってくることはあります。
営業の自由がありますから。
しかし、この法律で規制されていない商品は、相当難しいスキームであったり、リスクが高いものであったりするはずです。あるいは、もしかしたら詐欺的なものもあるでしょう。
普通に生活する中で、この法律で規制されている以外の金融商品で、資産を運用する必要があることはまずありません。
向こうからやってくる投資話、金融商品については、十分注意してください。
この法律に対する知識として、まずは、投資は自己責任、国は基本的に金融商品を個別に売りにいくことを禁止しているのだということを押さえて下さい。
2007年03月28日
もんじゃ焼き「月島」
のもんじゃ焼きがおいしいので、よく行きます。
ただし、いつも多いので土日は時間をずらして行かないとなかなか入れません。
先日は、平日を狙って行ってきました。
福岡ではあまりもんじゃ焼きの店は多くないように思いますが、ここのもんじゃ焼きは、本場東京とは少し異なっており、博多風もんじゃ焼きという感じがします。
しかし、東京の下手なもんじゃ焼き店よりも断然おいしいです。
基本的には、店員さんが焼いてくれるのですが、私は相当前から(4年以上経ちますかね)通ってますので、昨日今日入ったバイトさんより、断然上手に焼ける自信があります(笑)。
なので、いつも自分で焼いています。
もんじゃ焼きは作り方次第で、同じ材料でも味が全然違います(と思います)。
今日は、もんじゃ焼きのおいしい焼き方をお教えしましょう!
① 鉄板をよく熱して下さい。
ここが一番大事です。あせって、温度が低いままだとおいしくできません。
② 具材を炒める。
よくバラして、火を通して下さい。
③ キャベツを、汁気を残したまま、どさっと入れる。
キャベツの水分+少々の粉を溶いた水がいい感じにキャベツをしなっとしてくれるのです。
④ 具・キャベツを細かく切る
ヘラを上手に使って、細かくして下さい。
食感を楽しみたい人は、ざっとで構いません。が、ここで頑張る方がおいしいような気がします。
⑤ よく混ぜ合わせる
とにかく炒めて下さい
⑥ ドーナツ状に具を広げた後、真ん中に粉を溶いた水をいれ、水にとろみがつくまで待つ
この時、水を入れすぎると周りからこぼれでて、鉄板上がえらいことになります(笑)
ここの分量は経験ですね(笑)
⑦ ぐわーと混ぜる
⑧ ⑥・⑦を水がなくなるまで繰り返す
⑨ できる限り、広くのばす
薄ければ薄いほど、おいしいです
⑩ かつおぶし、青のり、ソース、マヨネーズをかけて完成!
「さあ、召し上がれ」
お店に書いてある作り方とは、若干違いますが、長年の研究によりこちらの方がおいしくできると思います。
ぜひ一度、お試し下さい。
お店は、麦野店、小田部店、春日店があります。
ただし、いつも多いので土日は時間をずらして行かないとなかなか入れません。
先日は、平日を狙って行ってきました。
福岡ではあまりもんじゃ焼きの店は多くないように思いますが、ここのもんじゃ焼きは、本場東京とは少し異なっており、博多風もんじゃ焼きという感じがします。
しかし、東京の下手なもんじゃ焼き店よりも断然おいしいです。
基本的には、店員さんが焼いてくれるのですが、私は相当前から(4年以上経ちますかね)通ってますので、昨日今日入ったバイトさんより、断然上手に焼ける自信があります(笑)。
なので、いつも自分で焼いています。
もんじゃ焼きは作り方次第で、同じ材料でも味が全然違います(と思います)。
今日は、もんじゃ焼きのおいしい焼き方をお教えしましょう!
① 鉄板をよく熱して下さい。
ここが一番大事です。あせって、温度が低いままだとおいしくできません。
② 具材を炒める。
よくバラして、火を通して下さい。
③ キャベツを、汁気を残したまま、どさっと入れる。
キャベツの水分+少々の粉を溶いた水がいい感じにキャベツをしなっとしてくれるのです。
④ 具・キャベツを細かく切る
ヘラを上手に使って、細かくして下さい。
食感を楽しみたい人は、ざっとで構いません。が、ここで頑張る方がおいしいような気がします。
⑤ よく混ぜ合わせる
とにかく炒めて下さい
⑥ ドーナツ状に具を広げた後、真ん中に粉を溶いた水をいれ、水にとろみがつくまで待つ
この時、水を入れすぎると周りからこぼれでて、鉄板上がえらいことになります(笑)
ここの分量は経験ですね(笑)
⑦ ぐわーと混ぜる
⑧ ⑥・⑦を水がなくなるまで繰り返す
⑨ できる限り、広くのばす
薄ければ薄いほど、おいしいです
⑩ かつおぶし、青のり、ソース、マヨネーズをかけて完成!
「さあ、召し上がれ」
お店に書いてある作り方とは、若干違いますが、長年の研究によりこちらの方がおいしくできると思います。
ぜひ一度、お試し下さい。
お店は、麦野店、小田部店、春日店があります。
2007年03月28日
ふくれんの・・・
オレンジジュースにはまっています。
そんなに値段も高くもなく、パックなので便利です。
濃縮還元でなく、ストレート果汁なので、後味すっきり。
みかんの味がきちんとします。
お風呂上がりには、これに限りますね!
小さいので大きなサイズも出してもらえると助かるのですが(笑)
2007年03月27日
ライブドア・負の訴訟連鎖へ
ニュースはこちら
フジテレビがライブドアに損害賠償請求を提起したそうです。
外野からみれば、どっちもどっちのような気もしますが、フジテレビの経営陣からすれば、やむを得ない措置なのでしょう。
すなわち、このまま放っておくと、自分達がフジテレビの株主から株主代表訴訟を提起されかねないという判断があったものと推測されるからです。
自分達の経営判断が間違っていなかったことを証明するためには、今回の訴訟で勝つことが何よりの証拠になりますから、フジテレビ経営陣にとって請求金額が実際にライブドアからもらえるか否かは、二の次の判断かもしれません。
しかし、請求内容が分からないので、何とも言えませんが、フジテレビも当然デューデリをしているはずですし、する機会はあったはずですから、粉飾を見逃した点はライブドア側から相当反駁されそうな気がします。
そうすると、本当に裁判までする必要があるのかという点も検討しなければなりません(もちろん、フジテレビでは検討した上での行動と思いますが)。
そうしないと、今度は自分達の面子のために無駄な裁判をしたとして、株主から訴訟提起されるリスクがでてきます。
フジテレビ経営陣からすると、進むも退くも難しい判断が求められているといったところでしょうか。
経営者は大変です。
ライブドアが上手くいっていれば、そもそもそんな心配はしなくてよかった訳ですから、これからの経営者は、相手方が粉飾や犯罪行為に手を染めてないか、その場合のリスクをどうヘッジするかまで考えていないといけないということですね。
とりあえず、裁判の行方を注目したいと思います。
フジテレビがライブドアに損害賠償請求を提起したそうです。
外野からみれば、どっちもどっちのような気もしますが、フジテレビの経営陣からすれば、やむを得ない措置なのでしょう。
すなわち、このまま放っておくと、自分達がフジテレビの株主から株主代表訴訟を提起されかねないという判断があったものと推測されるからです。
自分達の経営判断が間違っていなかったことを証明するためには、今回の訴訟で勝つことが何よりの証拠になりますから、フジテレビ経営陣にとって請求金額が実際にライブドアからもらえるか否かは、二の次の判断かもしれません。
しかし、請求内容が分からないので、何とも言えませんが、フジテレビも当然デューデリをしているはずですし、する機会はあったはずですから、粉飾を見逃した点はライブドア側から相当反駁されそうな気がします。
そうすると、本当に裁判までする必要があるのかという点も検討しなければなりません(もちろん、フジテレビでは検討した上での行動と思いますが)。
そうしないと、今度は自分達の面子のために無駄な裁判をしたとして、株主から訴訟提起されるリスクがでてきます。
フジテレビ経営陣からすると、進むも退くも難しい判断が求められているといったところでしょうか。
経営者は大変です。
ライブドアが上手くいっていれば、そもそもそんな心配はしなくてよかった訳ですから、これからの経営者は、相手方が粉飾や犯罪行為に手を染めてないか、その場合のリスクをどうヘッジするかまで考えていないといけないということですね。
とりあえず、裁判の行方を注目したいと思います。
2007年03月27日
桜の人
先日のインドの本と比較して読むと面白かった、この本。
日・中・米のスタイルを分析しています。
インドはどうという書き方よりも、この本のように比較対象を明示して書く方が、研究という面では優れてくるというのがよく分かりました。
(もちろん、インドの本がダメということではありません。)
一番よいと思ったのは、筆者(キャメル・ヤマモトさん)が自分の分析があくまでステレオタイプな分析だときちんと認識されていることです。
ステレオタイプな分析といえば、血液型や星座で性格を分析するものが思い浮かびますが、この本で書かれているのもその程度を出るものではないということを分かって書いているから、すばらしいのです。
血液型分析って結構当りますよね。
この本の分析も結構当ると思います。
ただ、血液型がB型だから、この人は絶対あまのじゃくだ!と最初から決めつけて、接することもあまりありませんよね(私の周りのB型は、ほとんどあまのじゃくですが。私も含めて(笑))。
その辺の使い分けができることを前提に、読める人にとっては、とても役に立つ本だと思います。
面白いですよ!
2007年03月26日
試験とネット
先日から、うちの事務所に今年度、2人目の司法修習生が来ています。
今回の修習生は、現役合格(大学生のうちに、司法試験に受かる)した方です。
彼に限らず、最近の司法試験は、法学部以外からの合格者(私もそうですね)や受験回数の少ない合格者が増えています。
したがって、合格者の顔ぶれも以前に比べると多様化しています。
それを見て、合格者の質が低下していると言う弁護士の方々も少なくありません。
しかし、私はそれは少し違うかなと思っています。
試験に通ることと、実力を身につけることは決して、イコールではありません。
試験はあくまでも、正解が設定された人為的なハードルです。
実務では、何が正解すらよく分からない場合がほとんどです。
試験に通るには、情報とその分析が必要です。
つい最近までは、情報を得て、その分析をするには、実際に司法試験を受けるしかありませんでした。
あるいは、合格した人の話を直接聞いて、感覚的なところを学んだりしていました。
したがって、どうしても情報が不足・偏ったりして、せっかくの努力が明後日の方向に向かってしまっていた人が少なくありませんでした。
しかし、ネットの登場で、情報収集は格段にやさしくなりました。
丁度、司法試験も60回を重ねつつあり、統計上の分析も十分可能になったのです。
予備校からの情報も地方にいても、過不足なく得られるようになりました。
試験は、傾向と対策で勝負が決まる部分が少なくありません。
東大には東大に受かるやり方、司法試験には司法試験に受かるやり方があります。
その分析が、法学部にいなくても、知り合いの先輩がいなくても自分で可能になったのです。
だから、他学部や現役合格生が増えているのだと思います。
この辺は、私の感覚的な理解ですが、将棋界の羽生さんが、プロになるための高速道路が出来たという表現をされているとおりだと思っています。
司法試験「合格」という目的だけに限ってみれば、長年勉強してきたこと自体は、さほどアドバンテージにならない時代になったのです。
しかし、試験と実力は異なります。
羽生さんは、高速道路の先で大渋滞が起きていると言われています。
法曹の世界も、早晩そうなるでしょう。
そこで問われるのは、やはり実力なのです。
日々精進、切磋琢磨していかないと生き残れません。
私も、毎日頑張ります!
今回の修習生は、現役合格(大学生のうちに、司法試験に受かる)した方です。
彼に限らず、最近の司法試験は、法学部以外からの合格者(私もそうですね)や受験回数の少ない合格者が増えています。
したがって、合格者の顔ぶれも以前に比べると多様化しています。
それを見て、合格者の質が低下していると言う弁護士の方々も少なくありません。
しかし、私はそれは少し違うかなと思っています。
試験に通ることと、実力を身につけることは決して、イコールではありません。
試験はあくまでも、正解が設定された人為的なハードルです。
実務では、何が正解すらよく分からない場合がほとんどです。
試験に通るには、情報とその分析が必要です。
つい最近までは、情報を得て、その分析をするには、実際に司法試験を受けるしかありませんでした。
あるいは、合格した人の話を直接聞いて、感覚的なところを学んだりしていました。
したがって、どうしても情報が不足・偏ったりして、せっかくの努力が明後日の方向に向かってしまっていた人が少なくありませんでした。
しかし、ネットの登場で、情報収集は格段にやさしくなりました。
丁度、司法試験も60回を重ねつつあり、統計上の分析も十分可能になったのです。
予備校からの情報も地方にいても、過不足なく得られるようになりました。
試験は、傾向と対策で勝負が決まる部分が少なくありません。
東大には東大に受かるやり方、司法試験には司法試験に受かるやり方があります。
その分析が、法学部にいなくても、知り合いの先輩がいなくても自分で可能になったのです。
だから、他学部や現役合格生が増えているのだと思います。
この辺は、私の感覚的な理解ですが、将棋界の羽生さんが、プロになるための高速道路が出来たという表現をされているとおりだと思っています。
司法試験「合格」という目的だけに限ってみれば、長年勉強してきたこと自体は、さほどアドバンテージにならない時代になったのです。
しかし、試験と実力は異なります。
羽生さんは、高速道路の先で大渋滞が起きていると言われています。
法曹の世界も、早晩そうなるでしょう。
そこで問われるのは、やはり実力なのです。
日々精進、切磋琢磨していかないと生き残れません。
私も、毎日頑張ります!
2007年03月26日
QBS5期生と
の懇親会が昨日ありました。
皆さん、やる気に溢れており、1年前の自分をみるようです(なんちゃって)。
1年も経つと、同期から、あれ?5期生?と言われるようになってしまいます(笑)。
4月からは真面目に学校に行きます・・・
5期生の皆さん、2年間(?)一緒に頑張りましょうね!
さて、MBAに財務の知識は欠かせないのですが、QBSの授業では英語の本が教科書です。
QBSには英語の得意な方が多いのですが、I have a pen.レベルの人間も(ここに)おりますので、翻訳本の入手が不可欠です。
去年は、教科書の版より古い翻訳しかなく、四苦八苦しておりましたが、今年は最新の翻訳本が出ています。
5期生の方だけでなく、財務に興味がある方、QBSって何を学ぶのだろうという方にもお勧めですので、ご紹介します。
財務を学ぶ者にとっては、イロハのイとなる教科書だそうです。
とても分厚い2冊組です・・・
とりあえず買ってみるのは、「上」だけというのがお勧めです(笑)
皆さん、やる気に溢れており、1年前の自分をみるようです(なんちゃって)。
1年も経つと、同期から、あれ?5期生?と言われるようになってしまいます(笑)。
4月からは真面目に学校に行きます・・・
5期生の皆さん、2年間(?)一緒に頑張りましょうね!
さて、MBAに財務の知識は欠かせないのですが、QBSの授業では英語の本が教科書です。
QBSには英語の得意な方が多いのですが、I have a pen.レベルの人間も(ここに)おりますので、翻訳本の入手が不可欠です。
去年は、教科書の版より古い翻訳しかなく、四苦八苦しておりましたが、今年は最新の翻訳本が出ています。
5期生の方だけでなく、財務に興味がある方、QBSって何を学ぶのだろうという方にもお勧めですので、ご紹介します。
財務を学ぶ者にとっては、イロハのイとなる教科書だそうです。
とても分厚い2冊組です・・・
とりあえず買ってみるのは、「上」だけというのがお勧めです(笑)
2007年03月24日
お笑いデビュー!
と言っても、私ではありません。
以前、私を相方に誘った、33歳大学生(会社員時代の同期です)が、今日、初舞台を踏みました。
場所は、福岡国際センター、「RKB春の感謝祭」でのイベントの中で、お笑いコンクールのようなもの(?)に出場することになりました。
今日はQBSの卒業式もあったし(3期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!こんなところですいません)、他の用事・業務もあり、ブッキングがすごかったのですが、人生初の正式な舞台ということで、とにもかくにも会社員時代の同期5人で応援に駆け付けたのです。
順番は2番目で、コンビで漫才を披露してくれました。
コンビ名は「タナ&パオ」・・・
う~ん・・・
微妙なコンビ名ですね(笑)
結果は、会場の喧噪がすごく、声が聞き取りにくかったことと、緊張していたのでしょう、テンポが悪く、ダダ滑りに滑っておりました。
ネタ的にも、客層と合わないようにも思いました。
選択ミスかなあ。
デビューにして、強烈な洗礼を浴びてしまったようです。
応援に行った私達は、ちょっとその場に居たたまれなくなって(笑)、みんなでそのままご飯を食べに行ってしまいました・・・
しかし、何事も経験してみないと分からないことの方が多いものです。
今回の経験は色々なことを教えてくれたはずです。
次回、なんとか立て直してきてくれることを期待しております。
がんばれ!「タナ&パオ」!!!
いや~、しかし「お笑い」恐るべしですね。
以前、私を相方に誘った、33歳大学生(会社員時代の同期です)が、今日、初舞台を踏みました。
場所は、福岡国際センター、「RKB春の感謝祭」でのイベントの中で、お笑いコンクールのようなもの(?)に出場することになりました。
今日はQBSの卒業式もあったし(3期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!こんなところですいません)、他の用事・業務もあり、ブッキングがすごかったのですが、人生初の正式な舞台ということで、とにもかくにも会社員時代の同期5人で応援に駆け付けたのです。
順番は2番目で、コンビで漫才を披露してくれました。
コンビ名は「タナ&パオ」・・・
う~ん・・・
微妙なコンビ名ですね(笑)
結果は、会場の喧噪がすごく、声が聞き取りにくかったことと、緊張していたのでしょう、テンポが悪く、ダダ滑りに滑っておりました。
ネタ的にも、客層と合わないようにも思いました。
選択ミスかなあ。
デビューにして、強烈な洗礼を浴びてしまったようです。
応援に行った私達は、ちょっとその場に居たたまれなくなって(笑)、みんなでそのままご飯を食べに行ってしまいました・・・
しかし、何事も経験してみないと分からないことの方が多いものです。
今回の経験は色々なことを教えてくれたはずです。
次回、なんとか立て直してきてくれることを期待しております。
がんばれ!「タナ&パオ」!!!
いや~、しかし「お笑い」恐るべしですね。
2007年03月23日
赤い彗星
シャアアズナブルの本が出ていましたので、有無を言わさず買いました。
赤い彗星シャアは、私の子供の頃からのヒーローであります。
「機動戦士ガンダム」という壮大な物語(ガンダム・サーガ)に欠かせない登場人物で、・・・とこれ以上説明すると、オタクのようになってしまうので、やめときます(笑)。
シャアザク格好良かったなあ・・・
この週末、読んでみます。
(ちなみにこれ、上下巻です。上下に分ける必要があるほどのボリュームではないですが。出版社の戦略を聞いてみたいですね)
2007年03月23日
九州大学第5回アジアラウンドテーブル
に行ってきました。
仕事により、途中退席ですが、聞きたかったシリコンバレーに行った九大生達の感想はしっかり聞いてこれたのでよかったです。
今回は、九州大学が行っているQREPというミッションで25名前後の学生(まれに社会人がまぎれていたようですが)が、シリコンバレーを見て、アントレプレナーシップを体感してきた感想と、そこで思い付いたビジネスプランを発表するのがメイン(?)でした。
詳しくは、九大坂本さんのブログをご覧下さい。
QBSからも、4期生1,2を争うエンターテナー、李さんが参加しています。
学生の発表は、シリコンバレーの熱気をそのまま持ち込んだように熱い気持ちをぶつけるもので、うらやましく聞いていました。
向こうでは、だれもが自分の好きなことを好きなだけ追い求めているようです。
来年、私もぜひとも行ってみたいなあと思っています。
4月から真剣に英語を勉強しようかな・・・
仕事により、途中退席ですが、聞きたかったシリコンバレーに行った九大生達の感想はしっかり聞いてこれたのでよかったです。
今回は、九州大学が行っているQREPというミッションで25名前後の学生(まれに社会人がまぎれていたようですが)が、シリコンバレーを見て、アントレプレナーシップを体感してきた感想と、そこで思い付いたビジネスプランを発表するのがメイン(?)でした。
詳しくは、九大坂本さんのブログをご覧下さい。
QBSからも、4期生1,2を争うエンターテナー、李さんが参加しています。
学生の発表は、シリコンバレーの熱気をそのまま持ち込んだように熱い気持ちをぶつけるもので、うらやましく聞いていました。
向こうでは、だれもが自分の好きなことを好きなだけ追い求めているようです。
来年、私もぜひとも行ってみたいなあと思っています。
4月から真剣に英語を勉強しようかな・・・
2007年03月23日
カレーうどん
今日のお昼は、一人だったので事務所近くの麺通団に行きました。
麺通団は、我が香川県の誇る田尾氏(元タウン情報かがわ編集長で、うどんの鬼・神様のような人です)がいっちょかみしているようなので、香川県人でも安心して(?)食べられる、さぬきうどんを出しています。
今日は、新メニューでカレーうどんがありました。丁度2週間に一、二度カレーが食べたくなる今日この頃の今の感じにぴたっときたので、迷わず、カレーうどんをオーダー。

1日20杯限定だそうです。
たしかにカレーはとてもおいしかったのですが、麺が・・・ むむむ???
ちょっとやわくない!?
博多人に合うようにカスタマイズしたのか?
それとも単にゆで時間を間違えたのか?
今までの麺とは若干異なるかも。
次回行った時が、最後とならないように、今度は気合いの入ったコシを期待しておきます。
麺はさておいて、カレーうどん、カレーが飛び跳ねて困ります(笑)
飛び跳ねないカレーうどん、なんとか発明してほしいものです。
今日は黄色っぽいジャケットだったので、大きな問題はなかったのですが。
(ジャケット着たまま食べる方が悪いんですけどね~)
麺通団は、我が香川県の誇る田尾氏(元タウン情報かがわ編集長で、うどんの鬼・神様のような人です)がいっちょかみしているようなので、香川県人でも安心して(?)食べられる、さぬきうどんを出しています。
今日は、新メニューでカレーうどんがありました。丁度2週間に一、二度カレーが食べたくなる今日この頃の今の感じにぴたっときたので、迷わず、カレーうどんをオーダー。

1日20杯限定だそうです。
たしかにカレーはとてもおいしかったのですが、麺が・・・ むむむ???
ちょっとやわくない!?
博多人に合うようにカスタマイズしたのか?
それとも単にゆで時間を間違えたのか?
今までの麺とは若干異なるかも。
次回行った時が、最後とならないように、今度は気合いの入ったコシを期待しておきます。
麺はさておいて、カレーうどん、カレーが飛び跳ねて困ります(笑)
飛び跳ねないカレーうどん、なんとか発明してほしいものです。
今日は黄色っぽいジャケットだったので、大きな問題はなかったのですが。
(ジャケット着たまま食べる方が悪いんですけどね~)
2007年03月23日
一歩も二歩も
他社より前にでないと、ベンチャーは立ち上がっていきません。
人と同じことしかしない、逆にいうと人と同じところであきらめていては、ベンチャー企業が経営を軌道に乗せることは至難の業といえるでしょう。
開発した技術がよければ、他人が自然と評価してくれるはず、あるいは特許が成立したら当然売れるはずと期待している技術者兼経営者の方は少なくありません。
残念ながら、「自分で他人の技術を根掘り葉掘り聞いては、評価する。」そんな暇な人はいません。
また、特許取得製品だから、買うという人もいません。
その商品に何らかの価値を見いだすから、人はモノやサービスを買うのであって、特許にお金を払っている訳ではないのです。
自分達の技術がいかに独創的で、画期的であるかは、独創的で画期的であればあるほど、何回もあるいはわかりやすく説明しないと他人は理解しないし、評価してくれないのです。
評価できないものに、人は価値を見いだすことはできません。
そこを勘違いして、大学や大手企業から評価してもらうのをひたすら待っているベンチャーが多すぎるように思います。
技術がすばらしいことと、それを理解させることは別次元の話です。
また、理解させることが自分は得意・不得意と言っている場合ではありません。
それができないと、生き残れないのです。
よい技術者は、よい経営者とは限らないという言葉は、その辺を指しているように思います。
よい技術を持っているからこそ、営業力が必要なのです。
技術を価値に換言する能力、これがベンチャーの立ち上がりを支える大事な能力のひとつです。
人と同じことしかしない、逆にいうと人と同じところであきらめていては、ベンチャー企業が経営を軌道に乗せることは至難の業といえるでしょう。
開発した技術がよければ、他人が自然と評価してくれるはず、あるいは特許が成立したら当然売れるはずと期待している技術者兼経営者の方は少なくありません。
残念ながら、「自分で他人の技術を根掘り葉掘り聞いては、評価する。」そんな暇な人はいません。
また、特許取得製品だから、買うという人もいません。
その商品に何らかの価値を見いだすから、人はモノやサービスを買うのであって、特許にお金を払っている訳ではないのです。
自分達の技術がいかに独創的で、画期的であるかは、独創的で画期的であればあるほど、何回もあるいはわかりやすく説明しないと他人は理解しないし、評価してくれないのです。
評価できないものに、人は価値を見いだすことはできません。
そこを勘違いして、大学や大手企業から評価してもらうのをひたすら待っているベンチャーが多すぎるように思います。
技術がすばらしいことと、それを理解させることは別次元の話です。
また、理解させることが自分は得意・不得意と言っている場合ではありません。
それができないと、生き残れないのです。
よい技術者は、よい経営者とは限らないという言葉は、その辺を指しているように思います。
よい技術を持っているからこそ、営業力が必要なのです。
技術を価値に換言する能力、これがベンチャーの立ち上がりを支える大事な能力のひとつです。
2007年03月22日
小麦色
今朝、通勤途中のラジオで、
「なぜ小麦粉は白いのに、日焼けした肌を小麦色というのか」というとても素朴な質問がリスナーから寄せられていました。
もちろん、小麦を挽いた粉と、実った小麦そのものの違いから来ているのですが、私がそれを聞きながら思ったのは、小麦色という色はいつから付いたのか、だれが付けたのかということです。
最近は色にも色々あって、シャンパンゴールドやら、なんとかシルバー、どうのこうのブルーとか、1回聞いても間違いなく覚えられない色が増えてますよね。
最近の色の命名は、どこの誰がやっているのでしょうか。
染料メーカーが勝手に決めているのでしょうかね?
小麦色と命名した人は、たぶん空と農場が似合ういい人なんだろうな~と想像しますが、シャンパンゴールドと名付けた人は、まさか朝シャン(朝からシャンパン開けることです。最近話題の)してる??と思ってしまいます。
ご存じの方、いらっしゃれば、メールかコメントお願いします。
若干、朝から気になっております(笑)。
「なぜ小麦粉は白いのに、日焼けした肌を小麦色というのか」というとても素朴な質問がリスナーから寄せられていました。
もちろん、小麦を挽いた粉と、実った小麦そのものの違いから来ているのですが、私がそれを聞きながら思ったのは、小麦色という色はいつから付いたのか、だれが付けたのかということです。
最近は色にも色々あって、シャンパンゴールドやら、なんとかシルバー、どうのこうのブルーとか、1回聞いても間違いなく覚えられない色が増えてますよね。
最近の色の命名は、どこの誰がやっているのでしょうか。
染料メーカーが勝手に決めているのでしょうかね?
小麦色と命名した人は、たぶん空と農場が似合ういい人なんだろうな~と想像しますが、シャンパンゴールドと名付けた人は、まさか朝シャン(朝からシャンパン開けることです。最近話題の)してる??と思ってしまいます。
ご存じの方、いらっしゃれば、メールかコメントお願いします。
若干、朝から気になっております(笑)。
2007年03月20日
タイこぼれ話その2
タイの街並みは、都心は日本とそんなに変わりませんが、大通りをはずれると、タイらしい感じになります。
都心はこんな感じです

ホテルの近くをぶらぶら歩いたのですが、雰囲気は、私が小さい頃いた、東大阪市の工場(こうじょうではなく、こうばの方です)が集まった地域によく似ているように思いました。
道路に面したプレス工場

があったり、鉄鋼資材卸やさんがあったり


人や車の通行よりも、自分達の商売が大事という感じが、なんとなく懐かしい感じです。
おそらく、この風景もこれから10年後には全く変わっているのでしょうね。
都心はこんな感じです
ホテルの近くをぶらぶら歩いたのですが、雰囲気は、私が小さい頃いた、東大阪市の工場(こうじょうではなく、こうばの方です)が集まった地域によく似ているように思いました。
道路に面したプレス工場
があったり、鉄鋼資材卸やさんがあったり
人や車の通行よりも、自分達の商売が大事という感じが、なんとなく懐かしい感じです。
おそらく、この風景もこれから10年後には全く変わっているのでしょうね。
2007年03月19日
インド人はなぜゼロを見つけられたか
表題がすごく興味を引いたので、中身をあまり見ずに買いました。
読み終わりましたが、インド人がなぜゼロを見つけられたのか、私にはよく分かりませんでした(笑)。
内容は、「インド」の紹介でした!
それでも、インドの今や昔が分かって、値段分の価値はありましたよ~。
本や雑誌って高いと思いますか?
私は極めて安い買い物だと思っています。
確かにネットで情報を集めれば、ほとんどタダですけど、集めた情報はそのままでは、情報でしかないんですよね。
それを知識として集約し、場合によっては知恵に変えていくのは大変な時間と作業が必要となります。
インドの情報にしても、この本の内容まで整理しようと思えば、1週間や2週間ではほぼ無理でしょう。そのことだけを考えても、本は安い買い物です。
私の中では、新聞が一番費用対効果を考えると安いなあと思っていたのですが、最近の新聞は、どれも広告と「情報」しか載せていないので、ネットとほとんど変わりないくらいまで、知識取得媒体としては、レベルが落ちています。
読者数からいけば、まだ新聞の方が圧倒的に多数でしょうが、今のままの新聞のあり方では、早晩発行部数が減少していくように思います。
ネットとの関係でいくと、本も消えて無くなるのかという議論がよくありますが、私は知識の整理として、「本」という方法は、この先も残ると思います。
では、紙がなくなるかどうかですが、本当に紙のようなディスプレイが実用化されれば、なくなっていくかも知れませんね。
2007年03月18日
引っ越しといえば、
敷金の返還で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
判例により、賃借人が原状回復すべき範囲は絞られつつありますし、敷引きが無効とされる場合も結構ありますが、未だ賃貸人や管理会社から、理由のよく分からない請求額のまま、敷金と相殺されてしまっているケースも多いようです。
これから借りる方に、アドバイスをするとすれば、まず不動産業者のその場しのぎの言動を信じてはいけません。
もちろん、信頼のおける不動産業者の方も少なくないですが、仲介業者はそのシステム上、借りる人のためだけに仕事をしてくれる訳ではありませんので、注意が必要です。
つまり、彼らは成約に至ると、借りる人と貸す人のどちらからも手数料という名目でマージンをとることが普通で、それで経営が成立している場合がほとんどです。
そうすると、自然とどちらに対しても、都合のよいことばかり言うことになります。
借り主からのクレームを、適切に貸し主に伝えておらず、後でトラブルになるケースは少なくありませんが、そもそもそうなる前提が整っているのですから、当たり前といえば、当たり前です。
ですので、借り主は入居に当たり、気になることがあれば、口頭だけでなく、手書きでもいいので書面にしておくことが重要です。
後で言った言わないのトラブルを防ぐことができます。
原状回復についても、入居時の写真を残しておいたり、契約時に原状回復すべき項目をリスト化しておく等、事前にトラブルの種を摘んでおくと、お互い気持ちよく、契約を終了することができるでしょう。
今の法律上、借り主の地位が過剰ともいえる程、保護されているので、どうしても貸し主は感情的になりがちです。
双方が納得ずくで、契約を締結することが、一番の処方箋といえるでしょう。
判例により、賃借人が原状回復すべき範囲は絞られつつありますし、敷引きが無効とされる場合も結構ありますが、未だ賃貸人や管理会社から、理由のよく分からない請求額のまま、敷金と相殺されてしまっているケースも多いようです。
これから借りる方に、アドバイスをするとすれば、まず不動産業者のその場しのぎの言動を信じてはいけません。
もちろん、信頼のおける不動産業者の方も少なくないですが、仲介業者はそのシステム上、借りる人のためだけに仕事をしてくれる訳ではありませんので、注意が必要です。
つまり、彼らは成約に至ると、借りる人と貸す人のどちらからも手数料という名目でマージンをとることが普通で、それで経営が成立している場合がほとんどです。
そうすると、自然とどちらに対しても、都合のよいことばかり言うことになります。
借り主からのクレームを、適切に貸し主に伝えておらず、後でトラブルになるケースは少なくありませんが、そもそもそうなる前提が整っているのですから、当たり前といえば、当たり前です。
ですので、借り主は入居に当たり、気になることがあれば、口頭だけでなく、手書きでもいいので書面にしておくことが重要です。
後で言った言わないのトラブルを防ぐことができます。
原状回復についても、入居時の写真を残しておいたり、契約時に原状回復すべき項目をリスト化しておく等、事前にトラブルの種を摘んでおくと、お互い気持ちよく、契約を終了することができるでしょう。
今の法律上、借り主の地位が過剰ともいえる程、保護されているので、どうしても貸し主は感情的になりがちです。
双方が納得ずくで、契約を締結することが、一番の処方箋といえるでしょう。
2007年03月17日
引っ越しシーズン
ですね。
今日は、仕事でしたので、いつもどおり車で通勤していると、引っ越しのトラックが沢山駐車している風景をみることが出来ました。
引っ越しを人生で何十回もする人もいれば、1度もしない人もいるのでしょうね。
私は、香川から飯塚市(大学)に来るので1回、大学から社会人になるので1回、会社をやめて1回、今のところへ引っ越したのが最後ですから、4回しかありません。少ない方でしょうか。
引っ越しはとにかく面倒くさいですね(笑)。
もともと荷物が多いのに、整理整頓が苦手なので、引っ越しの度に、必要なものがどこかに消えてしまいます。
どの段ボールにいれたのかが思い出せない・・・、捨てたかな?、まあいつか出てくるだろうという感じで、おそらく同じものが数個、今も家のどこかにあるはずです(笑)
でも、新しい土地で新しい生活をするのは何となく楽しいですよね。
引っ越ししようかな~
今日は、仕事でしたので、いつもどおり車で通勤していると、引っ越しのトラックが沢山駐車している風景をみることが出来ました。
引っ越しを人生で何十回もする人もいれば、1度もしない人もいるのでしょうね。
私は、香川から飯塚市(大学)に来るので1回、大学から社会人になるので1回、会社をやめて1回、今のところへ引っ越したのが最後ですから、4回しかありません。少ない方でしょうか。
引っ越しはとにかく面倒くさいですね(笑)。
もともと荷物が多いのに、整理整頓が苦手なので、引っ越しの度に、必要なものがどこかに消えてしまいます。
どの段ボールにいれたのかが思い出せない・・・、捨てたかな?、まあいつか出てくるだろうという感じで、おそらく同じものが数個、今も家のどこかにあるはずです(笑)
でも、新しい土地で新しい生活をするのは何となく楽しいですよね。
引っ越ししようかな~