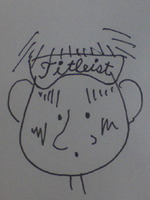2008年03月06日
キーマンはだれだ?
弁護士をしていると、様々な紛争が持ち込まれる訳ですが、その多くは、その紛争の中身というか内容を、例えば、法的な解釈や、それに基づくこちらの主張が、裁判になった場合に通る割合等々を相談されに来られます。
それは、それで大事な問題で、法的に争っても勝ち目が全くないのなら、早めに落としどころを見つけた方がいいですから、きちんと検討しなければなりません。
一方、その紛争を「交渉」と捉えたときには、それだけでは検討として不十分です。
こちらが、100%正しい、どう考えても何ら非を問われることがないというのは極々まれで、紛争になるからには、相手にもそれなりの言い分があるはずです。
したがって、紛争の解決を、「交渉」で行おうと思ったときは、紛争の論点、中身もさることながら、誰を相手にするのか、その相手とどれくらい交渉すべきなのかといった、交渉技術、交渉能力も重要になってきます。
その辺を理解せずに、こちらの法的な主張を一方的に言い続けるようでは、結局裁判所まで行かないといけないということになりがちです。
もちろん、裁判所まで行って、きちんと白黒つけるべき事件や紛争もありますので、一概に「交渉」で終わらせることを勧めている訳ではありません。
しかし、時間や費用等、その紛争にかかるコストを考えた場合に、訴訟ではなく、なんとか交渉で決着をつけたいということがあるはずです。
そんなときは、やはり、交渉能力が重要になってくるのです。
交渉においては、キーマンが誰かを見極める必要があります。
こう書くと、すぐにそのキーマンと直接、すぐに話しをしようとする、すればいいと考えがちですが、そうではありません。
キーマンとは、しかるべき時に、しかるべき内容で、話をしないといけないのです。
例えば、こちらが何らかの商品を買った側で、その商品にトラブルがあり、損害を賠償してもらいたいと思ったとき、すぐに「責任者をよべ、支店長を、社長をよべ」と言いがちではないですか?
しかし、それでは、相手の提案の余白というか余地を全く奪ってしまうことになり、呼ばれた支店長や社長からは、通り一遍の回答しか引き出せません。
決裁権を持つ人物と会って、話をするには、地ならしをしてからの方が得策です。
決裁権者に、「仕方ないですね、分かりました」と言わせる工夫が、交渉をまとめるためには必要なのです。
逆に、自分が求められる立場に立った場合には、いきなり決裁権者を出しては、いけないということになります。
弁護士を代理人に立てるのも、決裁権者の前にワンクッションを置くという意味があるのです。
それから、会社での立場が上でも、その人物には、意外に実際の決裁権限がないということもよくあります。
例えば、大企業では、本社のヒラ常務より、営業部隊の九州支社長の方が、現場の問題の決裁権限が大きいということもあり得ます。
相手のキーマンをいつ、どのタイミングで呼び出すか。
これが、交渉のキモといってもいいでしょう。
弁護士に相談・依頼にいくときは、これは裁判にしたくないなあと思ったら、その辺の機敏が分かる人に依頼するといいでしょうね。
それは、それで大事な問題で、法的に争っても勝ち目が全くないのなら、早めに落としどころを見つけた方がいいですから、きちんと検討しなければなりません。
一方、その紛争を「交渉」と捉えたときには、それだけでは検討として不十分です。
こちらが、100%正しい、どう考えても何ら非を問われることがないというのは極々まれで、紛争になるからには、相手にもそれなりの言い分があるはずです。
したがって、紛争の解決を、「交渉」で行おうと思ったときは、紛争の論点、中身もさることながら、誰を相手にするのか、その相手とどれくらい交渉すべきなのかといった、交渉技術、交渉能力も重要になってきます。
その辺を理解せずに、こちらの法的な主張を一方的に言い続けるようでは、結局裁判所まで行かないといけないということになりがちです。
もちろん、裁判所まで行って、きちんと白黒つけるべき事件や紛争もありますので、一概に「交渉」で終わらせることを勧めている訳ではありません。
しかし、時間や費用等、その紛争にかかるコストを考えた場合に、訴訟ではなく、なんとか交渉で決着をつけたいということがあるはずです。
そんなときは、やはり、交渉能力が重要になってくるのです。
交渉においては、キーマンが誰かを見極める必要があります。
こう書くと、すぐにそのキーマンと直接、すぐに話しをしようとする、すればいいと考えがちですが、そうではありません。
キーマンとは、しかるべき時に、しかるべき内容で、話をしないといけないのです。
例えば、こちらが何らかの商品を買った側で、その商品にトラブルがあり、損害を賠償してもらいたいと思ったとき、すぐに「責任者をよべ、支店長を、社長をよべ」と言いがちではないですか?
しかし、それでは、相手の提案の余白というか余地を全く奪ってしまうことになり、呼ばれた支店長や社長からは、通り一遍の回答しか引き出せません。
決裁権を持つ人物と会って、話をするには、地ならしをしてからの方が得策です。
決裁権者に、「仕方ないですね、分かりました」と言わせる工夫が、交渉をまとめるためには必要なのです。
逆に、自分が求められる立場に立った場合には、いきなり決裁権者を出しては、いけないということになります。
弁護士を代理人に立てるのも、決裁権者の前にワンクッションを置くという意味があるのです。
それから、会社での立場が上でも、その人物には、意外に実際の決裁権限がないということもよくあります。
例えば、大企業では、本社のヒラ常務より、営業部隊の九州支社長の方が、現場の問題の決裁権限が大きいということもあり得ます。
相手のキーマンをいつ、どのタイミングで呼び出すか。
これが、交渉のキモといってもいいでしょう。
弁護士に相談・依頼にいくときは、これは裁判にしたくないなあと思ったら、その辺の機敏が分かる人に依頼するといいでしょうね。