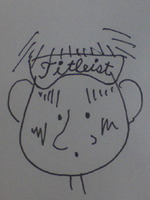2007年03月16日
意外な判決!?
ニュースはこちら

堀江被告人(テレビ、新聞では、相変わらず「被告」ですが、刑事裁判では「被告人」と言います。堀江氏の民事裁判の時の呼称は、「被告」です。)の判決がでましたが、皆さんの感想はいかがだったでしうか?
私は訴状も見ていないし、証拠も全く見ていないので、実刑が相当か否か分かりません。
社会的制裁を受けているとも思えるし、何ら受けてないとも言えますし。
判断は難しかっただろうと思います。
ニュースにあるように、宮内氏が自己の不正流用を問われないように検察に迎合した可能性も全くゼ
ロとは言い切れないかもしれません。
控訴するのであれば、宮内氏の供述の信用性が争点になるのでしょうか。
さて、ホリエモンが残した教訓は、法律上のグレーか否かを判断するのは、自分ではなく他者(裁判所等)だということに尽きるように思います。
新しいビジネスをしようという時には、必ず法律上の問題が生じます。
誰も思いついていない方法は、逆に、誰にも咎められたことがないからです。
「ルール違反」は明白ですが、「ルールを創造する」行為がどう評価されるのか、創造時には分かりません。
革命が成功すれば、内乱罪が適用されないとの同じことですね。
法律は全知全能の神がつくるものではありません。
人間が現状を把握して、追認する形でしか出来てきません。
現実より法律は常に一歩遅れるのです。
一方、ビジネスでは他者より一歩遅れていては、利益を得ることは難しい。
したがって、開拓者は常に法律上白か黒か、はたまたグレーかを考えながら、行動しなければならないのです。
白なら何の問題もありません。(あまり儲からないことも明白かもしれませんが)
黒でも何の問題もありません。(やったら駄目に決まってますね)
問題なのはグレーな時です。
法律上何の規定もないけれど、直感的に大丈夫だろうか?と感じるものが一番、他者より先駆けて行う価値のあるビジネスであることが多いようです。
堀江氏は、自分で白に限りなく近いグレーだと判断して、結果的に裁判所に黒と判断されました。
グレーだけどアウトとするか、グレーだけどセーフとするかはほんのわずかな判断の違いかもしれません。
でも、「その判断をするのは、全くビジネスの分からない人かも知れない。現実のビジネスの競争がどれほど厳しいか、百回説明しても実感してもらえない人かも知れない。」という想像力があれば、堀江氏の判断はだいぶ変わっていたように思います。
特に日本では、ビジネスを理解している裁判官は少ないと言ってよいでしょう。
裁判所に持ち込まれた時、自分たちの理屈がどの程度理解されるか、受け入れられるかを考える必要があります。
そのときに、日本は遅れているんだ!といってもはじまりません。
日本でビジネスをするのであれば、日本の法律と裁判所から逃れることはできません。
その中で、堀江氏のリーガルリスクの判断としては、やはり甘かったと言わざるをえないのかも知れませんね。
今回の裁判官がビジネスを理解していないということではありません。
そういう可能性もあるということを踏まえた上で、経営者は、未開の地へその一歩踏み出していかなければならないのだということです。
よくよく考えれば、経営者というのは、本当に大変な仕事ですね。
名経営者と言われる方が、自分とは異なる判断をしてくれる人を、常に身近に置いておきたくなる心境がよく分かります。
自分に従う意見ばかりの人を揃えると、ろくなことがおきないのでしょう。

堀江被告人(テレビ、新聞では、相変わらず「被告」ですが、刑事裁判では「被告人」と言います。堀江氏の民事裁判の時の呼称は、「被告」です。)の判決がでましたが、皆さんの感想はいかがだったでしうか?
私は訴状も見ていないし、証拠も全く見ていないので、実刑が相当か否か分かりません。
社会的制裁を受けているとも思えるし、何ら受けてないとも言えますし。
判断は難しかっただろうと思います。
ニュースにあるように、宮内氏が自己の不正流用を問われないように検察に迎合した可能性も全くゼ
ロとは言い切れないかもしれません。
控訴するのであれば、宮内氏の供述の信用性が争点になるのでしょうか。
さて、ホリエモンが残した教訓は、法律上のグレーか否かを判断するのは、自分ではなく他者(裁判所等)だということに尽きるように思います。
新しいビジネスをしようという時には、必ず法律上の問題が生じます。
誰も思いついていない方法は、逆に、誰にも咎められたことがないからです。
「ルール違反」は明白ですが、「ルールを創造する」行為がどう評価されるのか、創造時には分かりません。
革命が成功すれば、内乱罪が適用されないとの同じことですね。
法律は全知全能の神がつくるものではありません。
人間が現状を把握して、追認する形でしか出来てきません。
現実より法律は常に一歩遅れるのです。
一方、ビジネスでは他者より一歩遅れていては、利益を得ることは難しい。
したがって、開拓者は常に法律上白か黒か、はたまたグレーかを考えながら、行動しなければならないのです。
白なら何の問題もありません。(あまり儲からないことも明白かもしれませんが)
黒でも何の問題もありません。(やったら駄目に決まってますね)
問題なのはグレーな時です。
法律上何の規定もないけれど、直感的に大丈夫だろうか?と感じるものが一番、他者より先駆けて行う価値のあるビジネスであることが多いようです。
堀江氏は、自分で白に限りなく近いグレーだと判断して、結果的に裁判所に黒と判断されました。
グレーだけどアウトとするか、グレーだけどセーフとするかはほんのわずかな判断の違いかもしれません。
でも、「その判断をするのは、全くビジネスの分からない人かも知れない。現実のビジネスの競争がどれほど厳しいか、百回説明しても実感してもらえない人かも知れない。」という想像力があれば、堀江氏の判断はだいぶ変わっていたように思います。
特に日本では、ビジネスを理解している裁判官は少ないと言ってよいでしょう。
裁判所に持ち込まれた時、自分たちの理屈がどの程度理解されるか、受け入れられるかを考える必要があります。
そのときに、日本は遅れているんだ!といってもはじまりません。
日本でビジネスをするのであれば、日本の法律と裁判所から逃れることはできません。
その中で、堀江氏のリーガルリスクの判断としては、やはり甘かったと言わざるをえないのかも知れませんね。
今回の裁判官がビジネスを理解していないということではありません。
そういう可能性もあるということを踏まえた上で、経営者は、未開の地へその一歩踏み出していかなければならないのだということです。
よくよく考えれば、経営者というのは、本当に大変な仕事ですね。
名経営者と言われる方が、自分とは異なる判断をしてくれる人を、常に身近に置いておきたくなる心境がよく分かります。
自分に従う意見ばかりの人を揃えると、ろくなことがおきないのでしょう。
Posted by たばやん at 18:46│Comments(0)
│ベンチャー