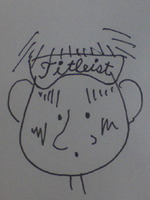2008年07月02日
「自粛」を「要請」?
ニュースは、こちら
温暖化防止のために、24時間営業を止めることがどれほど役立つのか、よく分かりませんが、こういう議論、日本では繰り返しなされて、独特の論理ですよね。
自粛とは、自らの意思で行うことではないのでしょうか?
要請された結果、行うことはそれはもう「自粛」ではないですよね。
優勝のビールかけを自粛。(「もったいない」の議論?)
番組放送を自粛。(「事件の影響」の議論?)
危険物の販売を自粛。(「模倣犯への影響」の議論?)
立候補を自粛。(「多選の是非」の議論?)
今まで数限りない自粛があり、それが要請されたものであったことも数多くあったはずです。
まるで、魔法の言葉のように「自粛」が使われていますが、どうなんでしょうか?
確かに、法的規制を課す(立法)には、時間的に猶予がないとか、法的規制を課すまでもないけど、できればしない方がいいかな。と誰もが思う時に、誰かが「自粛」を「要請」すると、便利ですよね。
日本的メンタリティとしては、和を持って、事態を収拾という感じになりますし、それはそれでメリットがあるのは分かります。
が、「自粛」と「要請」が、社会での、見えないルールになることは、やはり健全な状態ではないと思います。
また、誰が「要請」するのか、していいのかも大きな問題ですよね。
本来、自粛するかどうかは、その人、企業が自主的に判断すること。
その意味で、コンビニ業界の反対は、当然です。
それを、見えない空気で押し込める社会は、もはや法治国家ではないように思いますが、言い過ぎでしょうか。
基本的には、ルールは、「法」で決めていく。
この原則・考え方が、この国ではどっかに行ってしまった(あるいは最初からなかったような気もしますが)頃から、おかしくなってきたように思います。
誰でも事前に、ルールが分かること。
これが、プレーヤーとして参加できる最低限の条件だと思うのですが、日本というゲームの、ルールブックには、見えないルールがいっぱい書いてありますよね。
それでは、参加者は増えるはずはないでしょう。
やむを得ず、参加していたプレーヤーも、他のゲーム(国)に乗り換えるかも知れませんよ。
見えないルールの端的なものが、「自粛」の「要請」だと思いますが、どうでしょうか。
温暖化防止のために、24時間営業を止めることがどれほど役立つのか、よく分かりませんが、こういう議論、日本では繰り返しなされて、独特の論理ですよね。
自粛とは、自らの意思で行うことではないのでしょうか?
要請された結果、行うことはそれはもう「自粛」ではないですよね。
優勝のビールかけを自粛。(「もったいない」の議論?)
番組放送を自粛。(「事件の影響」の議論?)
危険物の販売を自粛。(「模倣犯への影響」の議論?)
立候補を自粛。(「多選の是非」の議論?)
今まで数限りない自粛があり、それが要請されたものであったことも数多くあったはずです。
まるで、魔法の言葉のように「自粛」が使われていますが、どうなんでしょうか?
確かに、法的規制を課す(立法)には、時間的に猶予がないとか、法的規制を課すまでもないけど、できればしない方がいいかな。と誰もが思う時に、誰かが「自粛」を「要請」すると、便利ですよね。
日本的メンタリティとしては、和を持って、事態を収拾という感じになりますし、それはそれでメリットがあるのは分かります。
が、「自粛」と「要請」が、社会での、見えないルールになることは、やはり健全な状態ではないと思います。
また、誰が「要請」するのか、していいのかも大きな問題ですよね。
本来、自粛するかどうかは、その人、企業が自主的に判断すること。
その意味で、コンビニ業界の反対は、当然です。
それを、見えない空気で押し込める社会は、もはや法治国家ではないように思いますが、言い過ぎでしょうか。
基本的には、ルールは、「法」で決めていく。
この原則・考え方が、この国ではどっかに行ってしまった(あるいは最初からなかったような気もしますが)頃から、おかしくなってきたように思います。
誰でも事前に、ルールが分かること。
これが、プレーヤーとして参加できる最低限の条件だと思うのですが、日本というゲームの、ルールブックには、見えないルールがいっぱい書いてありますよね。
それでは、参加者は増えるはずはないでしょう。
やむを得ず、参加していたプレーヤーも、他のゲーム(国)に乗り換えるかも知れませんよ。
見えないルールの端的なものが、「自粛」の「要請」だと思いますが、どうでしょうか。