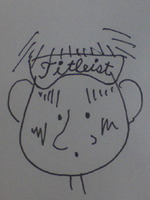2007年05月11日
大手といえども・・・
最近、大手企業からの契約書のチェックをすることがありました。
大手企業で法務もしっかりしているはずだから、そんなに問題ないだろうと思っていましたが、中身は・・・。
日本語になっていない条文もちらほらと・・・
契約書を作成する義務は、特別な法規制がない限り、ありません。
契約は口頭でも十分成立します。
それなのに、契約書を作成するのは、当該契約の意図を証拠として残すためです。
したがって、契約書を見れば、当事者間がどのような意図をもって、本件契約を結んだのかが分からないと作成する意味がありません。
例えば、当事者間で今回の契約が、スポット的な一回きりの契約なのか、今後の取引も予想される継続的な契約をしようとしているのか、あるいは、それぞれがどのようなリスクを捉え、それらをどう負担するようにしたのかという、当事者間の思惑が契約書から、透けて見えるのがよい契約書といえます。
文書から透けて見えれば、それを読む裁判官も当時の当事者間の思惑の心証がとれます。
紛争になったとき、証拠価値として十分なものとなるでしょう。
ですので、契約書には向こうの思惑だけが載るようなものではいけません。
ましてや、よく分からない表現の条文があったりしては、その契約の意図は契約書では全く証明できないことにもなり得ます。
とは言っても、大手企業は自分のところの定型の契約書の文言を変更することになかなか同意しないことがほとんどです。
その内容がまともであれば、いいのですが、中にはびっくりするようなものもあります。
彼らが変更をしないのは、実は、変更してもいいのかどうかが分からないだけではないのかと思えることもあります。
おかしな契約書で進めるしかないときは、他の方法で、契約の意図を残しましょう。
例えば、交渉の経緯を営業ノート等で随時、記録化しておけば、万が一の時の立派な証拠になります。
そのときだけでなく、継続的な記録をとる癖をつければ、営業のムダも見つかるかもしれません。
一石二鳥ですね(笑)。
研究者が発明の先後を争う時には、研究の過程を示したラボノートの存在がモノを言うときが少なくありません。
営業ノート、つけておくと助けられるかもしれません。
大手企業で法務もしっかりしているはずだから、そんなに問題ないだろうと思っていましたが、中身は・・・。
日本語になっていない条文もちらほらと・・・
契約書を作成する義務は、特別な法規制がない限り、ありません。
契約は口頭でも十分成立します。
それなのに、契約書を作成するのは、当該契約の意図を証拠として残すためです。
したがって、契約書を見れば、当事者間がどのような意図をもって、本件契約を結んだのかが分からないと作成する意味がありません。
例えば、当事者間で今回の契約が、スポット的な一回きりの契約なのか、今後の取引も予想される継続的な契約をしようとしているのか、あるいは、それぞれがどのようなリスクを捉え、それらをどう負担するようにしたのかという、当事者間の思惑が契約書から、透けて見えるのがよい契約書といえます。
文書から透けて見えれば、それを読む裁判官も当時の当事者間の思惑の心証がとれます。
紛争になったとき、証拠価値として十分なものとなるでしょう。
ですので、契約書には向こうの思惑だけが載るようなものではいけません。
ましてや、よく分からない表現の条文があったりしては、その契約の意図は契約書では全く証明できないことにもなり得ます。
とは言っても、大手企業は自分のところの定型の契約書の文言を変更することになかなか同意しないことがほとんどです。
その内容がまともであれば、いいのですが、中にはびっくりするようなものもあります。
彼らが変更をしないのは、実は、変更してもいいのかどうかが分からないだけではないのかと思えることもあります。
おかしな契約書で進めるしかないときは、他の方法で、契約の意図を残しましょう。
例えば、交渉の経緯を営業ノート等で随時、記録化しておけば、万が一の時の立派な証拠になります。
そのときだけでなく、継続的な記録をとる癖をつければ、営業のムダも見つかるかもしれません。
一石二鳥ですね(笑)。
研究者が発明の先後を争う時には、研究の過程を示したラボノートの存在がモノを言うときが少なくありません。
営業ノート、つけておくと助けられるかもしれません。