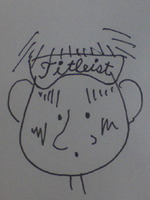2007年05月17日
食い逃げされてもバイトは雇うな
話題の作者の新書、今度は、上下巻のようですね。
マーケティングをしっかりしてきているのが伺えます。
内容は、専門家やビジネスをやっている人であれば、目新しいところは特にありません。
数字の持つインパクトなどは、マーケティング、広告を考える上では必須の知識ですからね。
しかし、この筆者のすごいところは、その説明力です。
非常に分かりやすい表現と、文体で噛み砕いて説明できるのは、すばらしい武器になります。
筆者は公認会計士をされているようですが、いわゆる「士」業では、その持っている知識の差はほとんどありません。国家試験で有る程度担保された人間しか、なっていない訳ですから。
差がつくのは、その知識をいかに顧客に分かりやすく示せるか、そのプレゼン能力と、ノウハウ、経験の蓄積というところにかかってくるように思います。
経験は、年数を重ね、件数を重ねないとすぐに備わるものではありませんので、若いうちは、いかに分かりやすく説明、納得させる話ができるかどうかが重要になってきますね。
その重要性を、再認識させてもらえた一冊となりました。
2007年05月17日
過払い返還請求と、経済原則
について、あまり深く考えられないまま、過払い返還を巡る規制や、各消費者金融会社の決算状況等が毎日、報道されています。
ニュースはこちら
私の業務でも、債務整理の中で、過払い金が生じていることが判明し、取り戻しの交渉をすることも多いですし、管財人業務として、破産した人の過去の取引履歴から、過払い金を発見し、破産財団に組入れ、配当を行うこともしばしばです。
福岡県弁護士会も、今月から多重債務相談については、無料で相談に応じるようになっており、ますます多重債務へのサポートは厚くなるでしょう。
そのこと自体はとてもいいことです。
また法律上、グレーの部分をなくすのも、とてもいいことです。
が、金利の上限を法律でむやみに決めてしまうことは、国の経済の死活問題になります。
その辺の意識がどの程度配慮されて、今回の貸金業法の改正が行われたのか。
少し不安になります。
金利が安ければ、いいじゃないかと思う方も多いかもしれません。
しかし、金融にとって、金利はまさにサービスの肝心要(かなめ)です。
それを規制されることは、商売そのものを規制されることに等しい行為です。
たとえば、出版社は、本の内容とページと装丁等を色々考えた上、販売価格を決めています。
これを、一律に1500円以上の値段に設定してはならないと法律で決まればどうでしょうか?
たとえば、自動車は、車種によって、色々なバージョンがあり、値段も様々ですが、法律によって、一律300万円以上の車は違法とされてはどうでしょうか?
自由な経済が停滞しはしないでしょうか?
金融についても、金利は、本来、融通先のレートと、貸出先のリスクを考慮して、貸主が自由に設定するべきものです。
それを見て、どこから調達するか、できるかを検討するのが、借り手の権利であり、責任です。
それは、まさに買いたい本や車を値段と内容を見て、決めるのと同じ理屈です。
したがって金利を法律で制限・固定するのは、自由経済国家ではないと断言できます。
貸金業法、ないし金利を制限する法律案には、そのようなリスクのある法律になるという意識が、この過払い金に関係する議論をしている人々の中には希薄なのではないでしょうか。
折しも、金融会社からは、そのような当たり前の主張がなされていますが、新聞には全く取り上げられていません。
無理な貸付、取立行為を制限すること、あるいは消費者を保護することと、金利の上限を制限することは、本来次元の異なる問題です。
冷静な議論をしておかないと、今後の日本経済は、結果的に今年を最大の分岐点(下降する方へ)とするような気がしてなりません。
ニュースはこちら
私の業務でも、債務整理の中で、過払い金が生じていることが判明し、取り戻しの交渉をすることも多いですし、管財人業務として、破産した人の過去の取引履歴から、過払い金を発見し、破産財団に組入れ、配当を行うこともしばしばです。
福岡県弁護士会も、今月から多重債務相談については、無料で相談に応じるようになっており、ますます多重債務へのサポートは厚くなるでしょう。
そのこと自体はとてもいいことです。
また法律上、グレーの部分をなくすのも、とてもいいことです。
が、金利の上限を法律でむやみに決めてしまうことは、国の経済の死活問題になります。
その辺の意識がどの程度配慮されて、今回の貸金業法の改正が行われたのか。
少し不安になります。
金利が安ければ、いいじゃないかと思う方も多いかもしれません。
しかし、金融にとって、金利はまさにサービスの肝心要(かなめ)です。
それを規制されることは、商売そのものを規制されることに等しい行為です。
たとえば、出版社は、本の内容とページと装丁等を色々考えた上、販売価格を決めています。
これを、一律に1500円以上の値段に設定してはならないと法律で決まればどうでしょうか?
たとえば、自動車は、車種によって、色々なバージョンがあり、値段も様々ですが、法律によって、一律300万円以上の車は違法とされてはどうでしょうか?
自由な経済が停滞しはしないでしょうか?
金融についても、金利は、本来、融通先のレートと、貸出先のリスクを考慮して、貸主が自由に設定するべきものです。
それを見て、どこから調達するか、できるかを検討するのが、借り手の権利であり、責任です。
それは、まさに買いたい本や車を値段と内容を見て、決めるのと同じ理屈です。
したがって金利を法律で制限・固定するのは、自由経済国家ではないと断言できます。
貸金業法、ないし金利を制限する法律案には、そのようなリスクのある法律になるという意識が、この過払い金に関係する議論をしている人々の中には希薄なのではないでしょうか。
折しも、金融会社からは、そのような当たり前の主張がなされていますが、新聞には全く取り上げられていません。
無理な貸付、取立行為を制限すること、あるいは消費者を保護することと、金利の上限を制限することは、本来次元の異なる問題です。
冷静な議論をしておかないと、今後の日本経済は、結果的に今年を最大の分岐点(下降する方へ)とするような気がしてなりません。