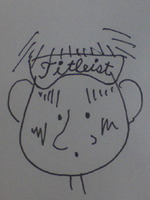2008年04月15日
リスクとリターン
ベンチャー企業を経営していて、頭が痛いのは、主に資金繰りと人材確保であるということは、このブログでも再三述べてきたとおりです。
そんな中、ベンチャーキャピタルから投資を受けるという選択肢は、ベンチャー企業経営者の頭の中に常にありうるものでしょう。
逆に、ベンチャーキャピタルから見向きもされないようであれば、まだまだ会社としては実力不足と思っていいかもしれません。
ご存じの通り、ベンチャーキャピタルやベンチャーファンドは、これは!と思うベンチャー企業に投資して、上場利益を得たり、株式譲渡益を得ることにより、自らの収益を上げようというものです。
会社に資金を「貸す」のではなくて、資金を「投資」して、大きな利益を得ようとするのが特徴です。
大きな利益が得られる可能性がある変わりに、投資ですから、会社が潰れれば、株式が無価値になる大きなリスクを負うことになります。
いわば、一か八かな面があることは否めません。
だからこそ、目利きが重要になり、「リスクテイカーである。」そこにこそ、ベンチャーキャピタルの社会的な存在価値があると思っていました。
思っていました。と過去形なのは、日本のVCでは、経営者の個人保証を求めることがあるという議論を最近、目にしたからです。
表明保証の信頼性担保のため、表明保証違反の際に、個人保証を求める条項を入れ込むことはまだ理解できます。
しかし、会社事業計画の未達の際にも、経営者に個人保証を求め、自己が出資した株式の簿価での買取を請求することがあるようです。
それでは、投資ではありません。単なる事業性資金の融資でしょう。しかも単なる融資より、たちが悪いと言わざるを得ません。
日本には、「リスク」と「リターン」をきちんと理解して、実行する土壌は生まれないのでしょうか(涙)。
最近のベンチャーキャピタルは、人材がそもそもそんなにいないため、銀行から流れてくることが多いです。
そのため、どうしても「融資」の発想で、「投資」をしたがるのかも知れません。
悪しき護送船団方式の影が、未だにちらついてなりませんね。
一刻も早く、リスクとリターンを適正に分配できる社会になってもらいたいと思います。
そのための市場が日本には、まだできていないというベンチャーキャピタルの声は分かるのですが、だからといって、それを経営者、起業家におっかぶせるのはやはり筋が通らない気がします。
そんな中、ベンチャーキャピタルから投資を受けるという選択肢は、ベンチャー企業経営者の頭の中に常にありうるものでしょう。
逆に、ベンチャーキャピタルから見向きもされないようであれば、まだまだ会社としては実力不足と思っていいかもしれません。
ご存じの通り、ベンチャーキャピタルやベンチャーファンドは、これは!と思うベンチャー企業に投資して、上場利益を得たり、株式譲渡益を得ることにより、自らの収益を上げようというものです。
会社に資金を「貸す」のではなくて、資金を「投資」して、大きな利益を得ようとするのが特徴です。
大きな利益が得られる可能性がある変わりに、投資ですから、会社が潰れれば、株式が無価値になる大きなリスクを負うことになります。
いわば、一か八かな面があることは否めません。
だからこそ、目利きが重要になり、「リスクテイカーである。」そこにこそ、ベンチャーキャピタルの社会的な存在価値があると思っていました。
思っていました。と過去形なのは、日本のVCでは、経営者の個人保証を求めることがあるという議論を最近、目にしたからです。
表明保証の信頼性担保のため、表明保証違反の際に、個人保証を求める条項を入れ込むことはまだ理解できます。
しかし、会社事業計画の未達の際にも、経営者に個人保証を求め、自己が出資した株式の簿価での買取を請求することがあるようです。
それでは、投資ではありません。単なる事業性資金の融資でしょう。しかも単なる融資より、たちが悪いと言わざるを得ません。
日本には、「リスク」と「リターン」をきちんと理解して、実行する土壌は生まれないのでしょうか(涙)。
最近のベンチャーキャピタルは、人材がそもそもそんなにいないため、銀行から流れてくることが多いです。
そのため、どうしても「融資」の発想で、「投資」をしたがるのかも知れません。
悪しき護送船団方式の影が、未だにちらついてなりませんね。
一刻も早く、リスクとリターンを適正に分配できる社会になってもらいたいと思います。
そのための市場が日本には、まだできていないというベンチャーキャピタルの声は分かるのですが、だからといって、それを経営者、起業家におっかぶせるのはやはり筋が通らない気がします。