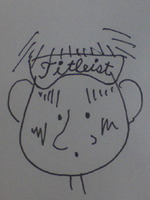2008年04月03日
事務局長就任(汗)
弁護士会では、公益等に関する活動として、各種委員会による活動を行っています。
例えば、消費者委員会は、消費者保護に関する問題を検討したり、シンポジウムを開催したりしています。
また、高齢者や福祉に関する委員会、基本的人権に関する委員会などもあります。
例えば、北九州市の生活保護申請に関する問題などでは、関係委員会に所属する弁護士が支援活動を行いました。
これらの委員会活動は、それによって収益が上がるものではなく、プロボノ活動や公益活動と呼ばれるものです。
弁護士に与えられた広範な権限に対応し、公的な責任を果たしていこうという趣旨で、長年、続いてきているものだと思っています。
最近の弁護士増員問題で、これら委員会活動を行う個々人の弁護士の余裕が、経済的にも時間的にもなくなるのではないかという懸念があります。
どうすればいいのか、いい知恵のある方、メール下さい(笑)。
結構、深くて難しい問題をはらんでいます。
で、私は、このブログでも何度か触れているとおり、「法教育」に関する活動を行う委員会に所属しています。
法教育とは、単なる法律知識教育ではなく、社会生活を営む上で必要な、「法的思考」を養うための教育論です。
それらに弁護士が関与することで、間違った「法概念」の押し付けにならないように、教育機関等と連携して、活動していこうという目的があります。
その委員会で、本年度からは、事務局長になることになりました(汗)。
事務局長の仕事は、まさに事務局で、裏方として様々な事務対応をするのが基本です。
以前は、弁護士3年目の若造がするようなポストではなかったのですが、最近は、弁護士会も年功序列が崩れてきて(笑)、いる人間(できる、できないではない!)に仕事をさせるようになってきているようです。
細かいことを整理するのは、昔から苦手なのですが、何事も経験と思って、やらざるを得ません。
法教育委員会では、今年、高校生を対象とした、模擬裁判選手権や、小・中学生を対象とした、ジュニアロースクールを開催する予定です。
法教育に関心のある方は、今後、適宜ご案内したいと思っていますので、ぜひぜひご参加下さい。
大人の方でも、見て頂ければ、相当面白いですよ!
法教育は、子供だけのものではありません。
例えば、消費者委員会は、消費者保護に関する問題を検討したり、シンポジウムを開催したりしています。
また、高齢者や福祉に関する委員会、基本的人権に関する委員会などもあります。
例えば、北九州市の生活保護申請に関する問題などでは、関係委員会に所属する弁護士が支援活動を行いました。
これらの委員会活動は、それによって収益が上がるものではなく、プロボノ活動や公益活動と呼ばれるものです。
弁護士に与えられた広範な権限に対応し、公的な責任を果たしていこうという趣旨で、長年、続いてきているものだと思っています。
最近の弁護士増員問題で、これら委員会活動を行う個々人の弁護士の余裕が、経済的にも時間的にもなくなるのではないかという懸念があります。
どうすればいいのか、いい知恵のある方、メール下さい(笑)。
結構、深くて難しい問題をはらんでいます。
で、私は、このブログでも何度か触れているとおり、「法教育」に関する活動を行う委員会に所属しています。
法教育とは、単なる法律知識教育ではなく、社会生活を営む上で必要な、「法的思考」を養うための教育論です。
それらに弁護士が関与することで、間違った「法概念」の押し付けにならないように、教育機関等と連携して、活動していこうという目的があります。
その委員会で、本年度からは、事務局長になることになりました(汗)。
事務局長の仕事は、まさに事務局で、裏方として様々な事務対応をするのが基本です。
以前は、弁護士3年目の若造がするようなポストではなかったのですが、最近は、弁護士会も年功序列が崩れてきて(笑)、いる人間(できる、できないではない!)に仕事をさせるようになってきているようです。
細かいことを整理するのは、昔から苦手なのですが、何事も経験と思って、やらざるを得ません。
法教育委員会では、今年、高校生を対象とした、模擬裁判選手権や、小・中学生を対象とした、ジュニアロースクールを開催する予定です。
法教育に関心のある方は、今後、適宜ご案内したいと思っていますので、ぜひぜひご参加下さい。
大人の方でも、見て頂ければ、相当面白いですよ!
法教育は、子供だけのものではありません。
2008年04月03日
てゆうか、まだなかったの?
ソースはこちら
国家戦略として、これからは知財だ、と言っておきながら、今までちゃんとした海外との窓口組織がなかったようです(汗)。
というか、まだまだ国家戦略としての体をなしていないんですよね。
知財でどうこの国を立て直すのか、何年先を見据えて、アクションプランを立てるのか、その実行は、どこがメインの司令塔で、どう行政機関及び民間との連携を取ってやっていくのか、そういった根本的な戦略立案を誰もしていない(ような)ので、相変わらず、各行政機関が自己に都合のよい解釈で、知財というお題目をうまく利用して、予算をぶんどっているにすぎない気がします。
ちょっと、言い過ぎでしょうか?
縦割り行政の弊害が、そこらかしこに散見されるのですが、それらを改善するために、また国家戦略を立てるための総合的な部門は、見当たりません。
知財さえあれば、どうにかなる訳ではありません(ここを勘違いしている企業や経営者も少なくありませんが)が、少なくとも基本的な知財戦略等を考えておかないと、えらいことになる時代です。
国として、企業として、どうするのか、そもそも戦略なき作戦は失敗しますよね・・・。
また詰めていない戦略に固執しても、失敗しますよね・・・。
どっちにも当てはまらないことを祈ります。
国家戦略として、これからは知財だ、と言っておきながら、今までちゃんとした海外との窓口組織がなかったようです(汗)。
というか、まだまだ国家戦略としての体をなしていないんですよね。
知財でどうこの国を立て直すのか、何年先を見据えて、アクションプランを立てるのか、その実行は、どこがメインの司令塔で、どう行政機関及び民間との連携を取ってやっていくのか、そういった根本的な戦略立案を誰もしていない(ような)ので、相変わらず、各行政機関が自己に都合のよい解釈で、知財というお題目をうまく利用して、予算をぶんどっているにすぎない気がします。
ちょっと、言い過ぎでしょうか?
縦割り行政の弊害が、そこらかしこに散見されるのですが、それらを改善するために、また国家戦略を立てるための総合的な部門は、見当たりません。
知財さえあれば、どうにかなる訳ではありません(ここを勘違いしている企業や経営者も少なくありませんが)が、少なくとも基本的な知財戦略等を考えておかないと、えらいことになる時代です。
国として、企業として、どうするのか、そもそも戦略なき作戦は失敗しますよね・・・。
また詰めていない戦略に固執しても、失敗しますよね・・・。
どっちにも当てはまらないことを祈ります。