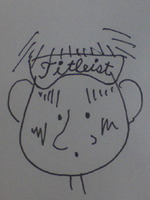2008年04月17日
今日雨なのも、自分の責任
昨日から、QBS3年目(笑)の授業がはじまりました。
単位は足りなかったものの、前期は1年生のときに張り切って取っている科目が多いので、逆に今年受けられる講義があまりありません。
前期では、3つか4つの科目を履修する予定です。
どれか、一つでも単位が取れれば、夏に卒業できます(恥)。
なので、講義自体は、こないだの土曜日からはじまってましたが、私のスタートは昨日から。
昨日の講義は、今年度から新しくできた「資産運用とリスク管理」という授業です。
今年度から新しくできた授業は、けっこうあって、3年目の授業料を払っても惜しくない、お得感があります(笑)。
昨日の授業は、金融商品市場の内情やファンドマネージャーの実際の行動等を学ぶことを通じて、リスク管理を考察するものになるようです。
担当の先生は、自己紹介をはっきりされませんでしたが(笑)、ディーラーの経験もあるそうで、話は面白かったです。
先生の話の中で、感心したのが、タイトルの言葉です。
金融市場の中に身を置いて、仕事をしていると、「自己責任」が身にしみる、というか、何でも自己責任であると思っておかないと、やってられない世界なのでしょうね。
最近の何でも人のせいにする風潮に、だいぶご立腹なようでした(笑)。
たしかに、雨に遭いたくないなら、前の日から、雨の降らない場所に移動しておけばよいわけで、それをしないで、雨が降ったのを天気のせいにするのは、リスク管理としては、甘いと言わざるを得ませんね。
結局、なんでも自己責任である。という考え方は、私は結構好きです。
司法試験も、難しいと言われてますが、受からないのを試験問題のせいにする人に限って、なかなか合格しなかったりします(笑)。
ロースクールに入ったものの、あまり上がらない合格率を聞いて、騙されたといっている方も、同じ穴のむじなでしょうか。
合格率が上がれば、自分も受かるのではないかという全く合理性のない理由を信じて、ロースクールに入るという選択肢を選んだのは、自分自身なのに。
そもそも、選択肢は、無数にあって、どれを選択するのかは、人それぞれの自由です。
自由なチョイスをした結果、その責任を問われるのはやはり自分自身。それしかないですよね。
働きたくなければ、働かなければいい。
勉強したければ、すればいいし、したくなければ、しなきゃいい。
年金をきちんとあげますよ。という国の方針を信じてしまったのも、自分自身ですよね。
その結果、どうなるのか、ちゃんと考えて、その選択をしたなら、それでいいはず、納得できるはずです。
しかし、その選択したのは自分なのに、その結果を受け入れない、受け入れられない人が増えているように思います。
そもそも選択することの意味やリスクとリターンを教えてもらってない、学んでない大人が多いのかも知れません。
でも、教えてもらってない。というのは、理由になりません。学ぼうと思わなかった自分の自己責任です(笑)。学ぼうと思えば、学ぶ機会(選択肢)はいくらでもあったはずです。
問題は、働きたいのに働けない。とか、勉強したいのにできない。という選択肢そのものを奪われている状況にある人が社会にいてはならないということです。
それは、本人の努力では、本当にどうにもならないものに限ります(なので、そうそう「選択肢そのものがない」という状況は、この国には、多くないはずです。選択肢はあるのに、それを選択しない、あるいはしたくない人は多いですが。)が、選択の余地がないのは、不公平・不平等です。競争原理や自由社会の前提を欠いています。
いずれにせよ、今後が、楽しみな授業になりそうです。
単位は足りなかったものの、前期は1年生のときに張り切って取っている科目が多いので、逆に今年受けられる講義があまりありません。
前期では、3つか4つの科目を履修する予定です。
どれか、一つでも単位が取れれば、夏に卒業できます(恥)。
なので、講義自体は、こないだの土曜日からはじまってましたが、私のスタートは昨日から。
昨日の講義は、今年度から新しくできた「資産運用とリスク管理」という授業です。
今年度から新しくできた授業は、けっこうあって、3年目の授業料を払っても惜しくない、お得感があります(笑)。
昨日の授業は、金融商品市場の内情やファンドマネージャーの実際の行動等を学ぶことを通じて、リスク管理を考察するものになるようです。
担当の先生は、自己紹介をはっきりされませんでしたが(笑)、ディーラーの経験もあるそうで、話は面白かったです。
先生の話の中で、感心したのが、タイトルの言葉です。
金融市場の中に身を置いて、仕事をしていると、「自己責任」が身にしみる、というか、何でも自己責任であると思っておかないと、やってられない世界なのでしょうね。
最近の何でも人のせいにする風潮に、だいぶご立腹なようでした(笑)。
たしかに、雨に遭いたくないなら、前の日から、雨の降らない場所に移動しておけばよいわけで、それをしないで、雨が降ったのを天気のせいにするのは、リスク管理としては、甘いと言わざるを得ませんね。
結局、なんでも自己責任である。という考え方は、私は結構好きです。
司法試験も、難しいと言われてますが、受からないのを試験問題のせいにする人に限って、なかなか合格しなかったりします(笑)。
ロースクールに入ったものの、あまり上がらない合格率を聞いて、騙されたといっている方も、同じ穴のむじなでしょうか。
合格率が上がれば、自分も受かるのではないかという全く合理性のない理由を信じて、ロースクールに入るという選択肢を選んだのは、自分自身なのに。
そもそも、選択肢は、無数にあって、どれを選択するのかは、人それぞれの自由です。
自由なチョイスをした結果、その責任を問われるのはやはり自分自身。それしかないですよね。
働きたくなければ、働かなければいい。
勉強したければ、すればいいし、したくなければ、しなきゃいい。
年金をきちんとあげますよ。という国の方針を信じてしまったのも、自分自身ですよね。
その結果、どうなるのか、ちゃんと考えて、その選択をしたなら、それでいいはず、納得できるはずです。
しかし、その選択したのは自分なのに、その結果を受け入れない、受け入れられない人が増えているように思います。
そもそも選択することの意味やリスクとリターンを教えてもらってない、学んでない大人が多いのかも知れません。
でも、教えてもらってない。というのは、理由になりません。学ぼうと思わなかった自分の自己責任です(笑)。学ぼうと思えば、学ぶ機会(選択肢)はいくらでもあったはずです。
問題は、働きたいのに働けない。とか、勉強したいのにできない。という選択肢そのものを奪われている状況にある人が社会にいてはならないということです。
それは、本人の努力では、本当にどうにもならないものに限ります(なので、そうそう「選択肢そのものがない」という状況は、この国には、多くないはずです。選択肢はあるのに、それを選択しない、あるいはしたくない人は多いですが。)が、選択の余地がないのは、不公平・不平等です。競争原理や自由社会の前提を欠いています。
いずれにせよ、今後が、楽しみな授業になりそうです。
2008年04月17日
刑事事件報道にBPO意見
ニュースは、こちら
光市の事件の報道を巡って、BPO(放送倫理・番組向上機構)から意見が出されたようです。
そもそも報道・放送の内容について、第三者機関とはいえ、一方的にああだこうだというのは、報道の自由の観点からみて、どうなのか?という気もしないでもないですが、意見としては、至極まっとうなものだと思います。
報道・放送を作る側が、あまりに無知ないし不正確であることは、受け手側の国民にとっても、不幸であるといえるのは、間違いないと思います。
せめて、「被告」ではなく、「被告人」と呼称するようにするとか、無罪推定の原則は理解しておくとか、送り手側としての最低限の責任は果たしておくべきですし、それが足りないのであれば、分かっている人間は指摘するべきです。
これまで、それらの指摘がなかったことが大きな問題だともいえますね。
マスコミやジャーナリズムは、市民が育てるものです。
知る権利と、報道・表現の自由は表裏一体なものと考えます。
マスコミの質は、国民の社会的な成熟を示すバロメーターでもあります。
この国の社会的成熟度の質は高いのか、低いのか、今まさに問われているように思います。
マスコミの成熟度という意味では、フランスやイギリスのマスコミ、特に新聞(ル・モンドやエコノミスト等)が思い浮かびますが、彼の国でも高尚なものから低俗なものまで、それはそれは幅広いですよね。
日本は、その幅が極めて狭い。しかも、感情的ものや低俗なものの方への分布率が高いように思いますが、どうでしょうか?
右でも左でもどっちでもいいですが、感情的ではない、論理的なポリシーがあるかないかは、成熟度に大きな影響を与えるといえそうです。
「感情」と「事実」を切り分ける冷静さと知識が、送り手側にも、受け手側にも求められているといえるのではないでしょうか。
光市の事件の報道を巡って、BPO(放送倫理・番組向上機構)から意見が出されたようです。
そもそも報道・放送の内容について、第三者機関とはいえ、一方的にああだこうだというのは、報道の自由の観点からみて、どうなのか?という気もしないでもないですが、意見としては、至極まっとうなものだと思います。
報道・放送を作る側が、あまりに無知ないし不正確であることは、受け手側の国民にとっても、不幸であるといえるのは、間違いないと思います。
せめて、「被告」ではなく、「被告人」と呼称するようにするとか、無罪推定の原則は理解しておくとか、送り手側としての最低限の責任は果たしておくべきですし、それが足りないのであれば、分かっている人間は指摘するべきです。
これまで、それらの指摘がなかったことが大きな問題だともいえますね。
マスコミやジャーナリズムは、市民が育てるものです。
知る権利と、報道・表現の自由は表裏一体なものと考えます。
マスコミの質は、国民の社会的な成熟を示すバロメーターでもあります。
この国の社会的成熟度の質は高いのか、低いのか、今まさに問われているように思います。
マスコミの成熟度という意味では、フランスやイギリスのマスコミ、特に新聞(ル・モンドやエコノミスト等)が思い浮かびますが、彼の国でも高尚なものから低俗なものまで、それはそれは幅広いですよね。
日本は、その幅が極めて狭い。しかも、感情的ものや低俗なものの方への分布率が高いように思いますが、どうでしょうか?
右でも左でもどっちでもいいですが、感情的ではない、論理的なポリシーがあるかないかは、成熟度に大きな影響を与えるといえそうです。
「感情」と「事実」を切り分ける冷静さと知識が、送り手側にも、受け手側にも求められているといえるのではないでしょうか。