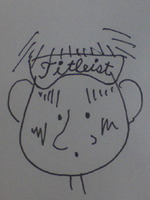2009年07月15日
中小企業に特許は不要!?
先週末の西日本新聞の経済面に、久しぶりに知財関連の記事が載っていました。
記事では、九州の中小企業の知財関連の現状が報告されており、我らが田中雅敏先生も顔写真付きでコメントを寄せていました。
記事の中でも印象深かったのは、地元企業経営者の声でした。
要約すると、中小企業にとって、特許は取っても意味がない。理由としては、当社も特許取得後、張り切って侵害者に対して警告をしたが、返す刀で、特許無効審判を起こされ、結果的に特許が無効になってしまった。その紛争にかけた弁護士費用(2つの事務所に依頼したそうです。)も莫大なものになったからというものでした。
刺激的な結論ですね。
たしかに、その社長さんの経験は、まさに「特許」の扱い方を間違えるとこうなりますという見本のようなもので、一面は真実を表しています。
しかし、私は、中小企業にとって、特許が不要とは全く思いません。
問題は、中小企業の経営陣において、特許とは単に取ればいいものではなく、その使い方、つまり戦略を持って、取得しなければならないものだという理解が一般的に不足していることだと思われます。
特許には、非常に荒っぽく言って、二通りの使い方があります。
一つは、お金を生むための特許。
もう一つは、お金を守るための特許。
同じ特許でも、使い方や性質が全く異なります。したがって、特許の取り方もだいぶ変わってきます。
しかし、経営者の方々は、とにかく特許が取れればいいと思っている方が多すぎます。
何のための特許かという視点の有無で、明細書に書く内容は大きく異なるはずです。
弁理士さんに頼むと、一枚いくらの世界ですから、とにかく枚数を少なくすることを第一とする経営者の方もいるでしょう。
しかし、費用には注目しても、その辺に無頓着なまま、目的の定まらない明細書にしてしまうと、後で大変なことになるのは当たり前といえば、当たり前なのです。
そして、結果的に、実は、お金を守るための特許としてしか取れていないのに、見誤って、それでお金を生もうとすると、先ほどの話のように、本来のお金を守るという目的を果たすことすら出来なくなるのです。
何のために、どのような特許を取るのか。
この命題なくして、特許を使いこなすことはできません。
命題を間違えて捉えると、せっかくの特許は意味を持たないどころか、経営を危うくすることにもなりかねません。
そのような特許の使い方のキモとなるところを、中小企業の経営者は、マスターするか、アドバイスをもらわないといけないのです。
また、特許だけで考えるのではなく、契約の方法等、トータル的な視点で、その技術を考える必要もあります。
無闇に特許申請して、公開してしまうことが必ずしもベターな方法ではないことは、例えばコカコーラを学べば、すぐ分かることです。
やっぱり、常に目的と手段の関係を忘れてはいけないということです。
特許もあくまでも、利益獲得という目的の一手段にすぎないのですから。
記事では、九州の中小企業の知財関連の現状が報告されており、我らが田中雅敏先生も顔写真付きでコメントを寄せていました。
記事の中でも印象深かったのは、地元企業経営者の声でした。
要約すると、中小企業にとって、特許は取っても意味がない。理由としては、当社も特許取得後、張り切って侵害者に対して警告をしたが、返す刀で、特許無効審判を起こされ、結果的に特許が無効になってしまった。その紛争にかけた弁護士費用(2つの事務所に依頼したそうです。)も莫大なものになったからというものでした。
刺激的な結論ですね。
たしかに、その社長さんの経験は、まさに「特許」の扱い方を間違えるとこうなりますという見本のようなもので、一面は真実を表しています。
しかし、私は、中小企業にとって、特許が不要とは全く思いません。
問題は、中小企業の経営陣において、特許とは単に取ればいいものではなく、その使い方、つまり戦略を持って、取得しなければならないものだという理解が一般的に不足していることだと思われます。
特許には、非常に荒っぽく言って、二通りの使い方があります。
一つは、お金を生むための特許。
もう一つは、お金を守るための特許。
同じ特許でも、使い方や性質が全く異なります。したがって、特許の取り方もだいぶ変わってきます。
しかし、経営者の方々は、とにかく特許が取れればいいと思っている方が多すぎます。
何のための特許かという視点の有無で、明細書に書く内容は大きく異なるはずです。
弁理士さんに頼むと、一枚いくらの世界ですから、とにかく枚数を少なくすることを第一とする経営者の方もいるでしょう。
しかし、費用には注目しても、その辺に無頓着なまま、目的の定まらない明細書にしてしまうと、後で大変なことになるのは当たり前といえば、当たり前なのです。
そして、結果的に、実は、お金を守るための特許としてしか取れていないのに、見誤って、それでお金を生もうとすると、先ほどの話のように、本来のお金を守るという目的を果たすことすら出来なくなるのです。
何のために、どのような特許を取るのか。
この命題なくして、特許を使いこなすことはできません。
命題を間違えて捉えると、せっかくの特許は意味を持たないどころか、経営を危うくすることにもなりかねません。
そのような特許の使い方のキモとなるところを、中小企業の経営者は、マスターするか、アドバイスをもらわないといけないのです。
また、特許だけで考えるのではなく、契約の方法等、トータル的な視点で、その技術を考える必要もあります。
無闇に特許申請して、公開してしまうことが必ずしもベターな方法ではないことは、例えばコカコーラを学べば、すぐ分かることです。
やっぱり、常に目的と手段の関係を忘れてはいけないということです。
特許もあくまでも、利益獲得という目的の一手段にすぎないのですから。
Posted by たばやん at 17:59│Comments(0)
│経営